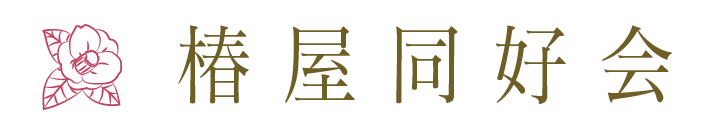シーフードミックス缶の中の手紙
シーフードミックス缶の中の手紙
Kabao
/1
私は第六昇降式貨物艇から吐き出される蟹甲複合繊維の選別をする仕事をしていた。白い半透明の、細長い繊維だ。塵肺防止用のマスクをしていたから、鼻や口は蒸し暑かったけど、問題は無い。衛生帽の中の髪の毛が、透明な繊維を巻き込んでキシキシするのをなんとか洗い流したいと思ったけど、空荷のリニアコンベアが赤子のようにビィビィと喚くから、そんな時間は無いのだった。
検品のために首を振る都度、キシキシとする黒髪を気にしながら、とうとう十六時間――その間に昼飯と夕飯の休みだけがあったのだけど、坐りこむ場所なんて無かった(産業機械の経路保持の名目で、人間が六十秒以上、同じ場所に坐っていると電気と突起で排除しようとしてくるからだ)から立ったまま携行食と栄養剤を飲み込むくらいしかできなかった。
一日の労働が心や骨に罅を入れる直前で終わって、私たちは圧縮空気と温いシャワーで洗われて、人間たちの世界に吐き出される。念入りに繊維屑を取るのは私たちの健康のためではない。真っ当な市民たちが私たちのせいで健康被害にあってはいけないからだ。
工場から外に出ると、第六昇降式貨物艇が天まで伸びるのが見える。ほぼほぼ天頂のあたり。衛星港にはぼってりとした種子みたいな船がひとつ。最新型の木星往還船だ。片道に一年と二百九十日をかけて、木星と地球を往復するらしい。あれだけ速い乗り物に乗ったら、私もどこかへ行けるのだろうか。乾いた空気に息を吐きながら、そんなことを思う。
帰路の途中。メトロにあるキオスクで『シーフードミックス』の缶詰と圧縮パンを買った。倒産した倉庫からの放出品だとかで、市場価格の半分以下だった。ざらざらとした、経年劣化した缶詰の手触り。古くなったラベル。それは、ただの新品のそれより、いくらか、温かく感じた。
深夜労働者が寝床に帰るこの早朝の時間は、金持ちたちは雑巾みたいな大きさのオムレツを食べるのに夢中だから、メトロの座席は万人に開放されている。私は残飯を漁るネズミのように細かく周囲を見渡してから、端っこの席に坐った。
重力から解放されると、見ないようにしていた疲れや痛みが一斉に顔を出してくる。もしも宙に浮かぶ星になれたならば、この草臥れから離れることができるのだろうか。どれだけ遠くに離れれば、この重さを振り切ることができるんだろう。
手のなかで、缶詰が重力を主張する。
この重さは、母を思い出す。
缶詰を買うとき、母は良く言っていた。地球は良い場所だと。一日の働きのほとんどを空費してもささやかな食事しか手に入らない場所のどこが良い場所なのだと思ったけど、浮浪児であった私を引き取って育ててくれた彼女がそう言ったのだから、私はその言葉を裏切るようなことができずにいた。
「ただいま、母さん」
真っ暗な部屋に帰る。母は若くして死んだ。持病――と言って良いのかはわからない。医者に掛かることもなく、干涸らびた人参のように肌をくすませ、痩せ細って、咳をしながら、自分の病の名すら知らずに死んでいった。
「ただいまって、言ってるんだけど」
部屋のなかに声をかける。返事はない。知っていることだ。誰も居ない。声は返ってこない。でも、その事実を確認するたびに何かが削れていくような気がした。
私は溜息をついて電気を付ける。無人の部屋に荷物を降ろして、小さな遺影に挨拶をする。残ったのは写真一枚と、遺灰を圧縮して作った人造ダイヤの一片だけだ。墓は無い。本物の家族も無い。家だって、いつまで残してあげられるか。
服を脱ぐ。工場のときみたいな、道具としての洗浄ではなく、人間の真似事をするみたいに丁寧に、シャワーで身体を洗う。温かいということを――例えば母のてのひらの温度を忘れてしまわないように、少し贅沢をして少し熱めの温度にするのが好きだった。
身体を拭き、ぼろを纏い、部屋の隅に坐る。坐るというのも贅沢な行為で、この瞬間、私はまさに地球の貴重な空間の一部を占有しているのだ。少しだけ愉快な気持ちが溢れて、小さな笑い声が口から漏れた。
シート状の圧縮パンの内袋の口を切ると、空気を呑み込んだパンが一気に膨れ上がる。匂いを嗅ぐ。悪くない。それから私は、一緒に買った缶詰を取り出した。
普段はこんな贅沢はしないけど、今日は母の命日だ。
半分ずつにして食べるなら悪くない。
「母さん、好きでしょ。シーフードミックス缶」
星空の遠くを見る母の目を想い出す。重力を振り切るぐらいの速度で一年と二百九十日も飛んだ場所に、この缶詰の工場はある。木星第八十衛星、メガロパだ。
木星のガスを吸って育つ巨大な蟹の幼体。生きる衛星。その背中を掘削して作られた工場で、これは作られている。母は給料が入る度にこの缶詰を買ってきて、綺麗に食べては、中にある半透明のシートまで綺麗に洗って保管していた。壁の遺影と遺骨のダイヤモンドの下には、綺麗な空き缶がうずたかく積み上げられている。
いつだったか。缶を棄てない理由を聞くと、母は恥ずかしそうに、これは私の生きた証なのだと言った。母には技術があったから私より稼げていたけど、それでも薄給だった。きっと月に一度の贅沢だったのだろう。今でこそ私の給金でも手が届くけど、異物混入騒ぎで価値が暴落する前は――いや、母が若かった頃なんて、貴族の晩餐に使われるような超高級品だったのだ。遠い異星から届く未知の生命体の肉。夢と希望に溢れた絶品の缶詰。すべてのシーフードをミックスしたような特別な味――まぁ、私はこれ以外の海産物を食べたことがないから、何の味に似てるかなんてわからないのだけど。
「じゃあ開けるよ。聞いてて」
どこかに居る母に向かって言う。母は缶詰の蓋を開ける音が好きだったからだ。いつも耳を近づけて、気泡のつぶれる音のひとつも聞き逃さないような、真剣な顔をしていたものだ。
カシュ。プルトップを引く。金属が金属を滑る手応えが指に伝わる。ゆっくりと引き上げていく。地球の空気が缶詰に流れ込んで、シーフードミックスの汁が跳ねる。
遠く。遠く。宇宙の彼方。時間と距離を旅してきた真空が、地球の空気と混ざり、地球の一部になっていく。
ようこそ、地球へ。
その浪漫が好きなのだと母はよく言っていた。
缶詰のなかには半透明な紙が入っている。それを開くと、中には肌の色を淡くしたような紐の束。これがシーフードミックスの筋肉だ。母が使っていた椀にそれを取り出して――。
「なんだろうこれ」
気付いた。シートに、半透明の、キラキラした模様がいっぱい入っているのだ。私は慌てて、母の遺品の缶詰からシートを取り出すが、そこには何も書かれていない。この缶詰のシートだけが、特別みたい。
情報端末を取り出してレンズを向ける。私が知らないことも、この機械は知っている。ポン、って音がして光学識別のアプリが勝手に起動した。合成音声の女の子が、私に向かって話しかけてくる。
《旧式の透過ホロコードです。読み取りますか?》
「はい。お願いします」
《承認取得。読取終了。音声情報と判断。再生しますか?》
「うーん。そうだね。聞かせてくれますか?」
《承知しました。それでは再生します――》
端末のちいさなスピーカーが、鮮明に、どこか違う場所の空気の振動を再現する。あちこちで機械の音がする。それから、少し古い共通語のような言葉。
そして、緊張したような若い女の人の咳払い。
『あ、あ、えっと、あの、』
声。日本語だ。驚いた。
私はスピーカーの音量を上げて、深呼吸をする。
一体、何が――
『――聞こえますか。私の言葉がわかりますか。あなたは日本の人ですか? 私が喋っているのは、日本語という名前の言葉で合っていますか? 私の名前はハヤマ・エナと言います。』
その声に、私は、釘付けになってしまった。
/2
――私はメガロパN製缶の缶詰を作る女工です。ここには世界中の言葉のラベルがあります。私はラベルを貼り付けるのが仕事です。私はいま、母や私が使っているのと同じ言葉のラベルを見つけたので、衝動的に端末を使って声を吹き込んでいます。聞き取れているでしょうか。メガロパの人間以外と話すのは初めてなので、不安です。でも共通語で喋っていたら誰かに中身を聞かれてしまいます。それは不本意なのです。私がこれからする話は、地球のあなたに届くまでぴったりと密閉された缶詰の中身のように、誰の耳にも届いてほしくないからです。聞き苦しいかもしれません。でも、どうか、最後まで、聞いてください。笑いものにしてくださってもかまわないのです。どうか、どうか、私の話を。私が愛した人の話を、地球の人の耳に、地球の空気に、一度で良いから触れさせてほしいのです。
私が労働している工場は、メガロパの第三左腹肢の付け根にありますから、左肢容器工場区画と呼ばれています。背中にある第二宇宙港から、内クチクラのメトロに乗って二時間なので、なかなか都会です。脚の付け根にも近く、メガロパが身動ぎをしてもあまり揺れないので快適な方だと思います。外と違って空気は不味いですが、奥深い内クチクラなのでヒルもあまりでません。
起きて、働き、食事をし、働き、働き、働き、食事をして、身体を清潔にして眠る。だいたいそういう生活です。地球ではどうでしょうか。地球には本物の朝と、本物の夜があると聞きます。本物の朝には、鳥という生き物が不思議な音を出すというのは本当ですか? それを聞いて目覚め、遊び、学び、働き、生きるという話を聞きました。
いえ。違いますね。
私たちが詰めている缶詰はとても高価で、地球でとっても良い暮らしをしている立派な人たちが食んでいると聞きました。ですからあなたはきっと、一日中、地球や、木星や、メガロパの人たちがより良く生きていくにはとか、そんな難しいことを考えておられるんじゃないですか?
そんな立派な人たちのなかに、私たちと同じ言葉を使う人が居て嬉しく思っています。この声を聞いているあなたは、いったいどんな暮らしをしている人なのでしょう。
牛という縞々の生き物は食べましたか? 本という紙の束に触ったことは? まだ富士という自然の構造物は残っていますか? 地面から温かいお湯が湧き出ていて、それに潜るという遊びがあるのは本当ですか?
話がそれてしまいました。
地球はどんな所ですか? よかったら言葉にしてみてくれませんか? ひょっとしたら、彼女に聞こえるかもしれない。彼女は日本語をあまり使えないですが、きっと届くかもしれないでしょう?
彼女っていうのは誰ですかって?
あぁ、名も聞けぬ地球のあなた。きっとそうお訊ねになったのではありませんか? わかりますとも。
そうやって話が迷子になるのが悪癖だと、彼女に何度も何度も言われてますから。えぇ。それが彼女に言わせると私という人間の特性なのだそうです。
――ええと、そう。彼女のことですね。名前はエレンと言います。勇敢な船乗りの名が由来だと言っていました。船というのは地球にもありますか? 深淵で遠大な星の海を渡る乗り物のこと……だ、そうです。
さてエレンは。私の大切な人は、私と同室の少女です。メガロパ・コロニーでは空気にも食料にも供給計画がありますから、労働者の数が徒に増えてしまっては拙いのです。労働を担当とする者は番いになって勝手に繁殖しないよう、女なら女同士で部屋を割り当てられ、一生を添い遂げます。私は母の三人目の娘でしたから、労働の役割が与えられました。同室になったエレンも、似たような所だと思います。
十二歳の時に、私たちは初めて顔を合わせ言葉を交わしました。驚きました。彼女はメガロパの共通語を使うだけで、日本語を喋れないのです。私はそれまでずっと、日本語を喋る人の居る地区に住んでいましたから、そんな人が居るとは思いもしませんでした。
驚いたのは、それだけではありません。彼女の髪の色は大赤斑のように明るく、肌の色はガニメデのように白く美しかったのです。それに比べたら私や母の髪はカリストのようであり、肌はエウロパやイオのようでした。
もちろん、共通語の教育は受けておりましたから、私はエレンと共通語を使って会話をしました。私たちはすぐに打ち解け、仲良くなり、互いを信頼しました。肌の色や使う言葉は違いましたが、心の形は一緒だったのだと思います。
私たちは新人の子たち十五人で一つの班になり、そこで半年かけて仕事を覚えました。ご存知のようにシーフードミックスの筋肉を真空缶詰にするのが私たちの労働です。一日仕事をするといくらかの給金と、三切れのパンと、シーフードミックスの端切れが貰えます。そう。なんて贅沢なことでしょう。いま、遠い地球で人類の行く末を悩む高貴なあなたが大金を出して食べている物と同じ物を――いいえ。もっと新鮮な物を、私たちは頂いているのです。地球に住む親愛なる名も聞けぬあなたは、それを羨ましいと思ってくださるでしょうか。
――さて。私たちの班はみな、優秀でした。特にエレンは何も見ないでもまっすぐにラベルを貼ることができます。彼女の細く柔らかな指が、缶をくるくると回す所を見るのが私は好きでした。どうしてそんなに指が美しいのか訊ねると、彼女はその真白い頬を赤くして、爪に塗り薬を塗っているからだと言いました。私が興味深そうにしていると、その日の夜、彼女はこっそりと私の左の手に、その塗り薬を塗ってくれました。彼女の美しさの幾分かが自分の手にも宿ったような気がして、その日は眠ることができなかったほどです。
ひょっとして、どうして機械を使わないのか、不思議に思われましたか? そうでしょう。わかります。あの無骨で強く、疲れず、壊れない黒鉄ではなく、この容易く砕ける細い指を使って、なんで缶詰なんかを作っているのだろう。そう不思議に思われたのでは無いですか? 私たちだって、地球はそういう所だと聞いています。働いている人の数より、働いている機械の数の方が多いのでしょう? なんて素晴らしいことでしょうか。でもメガロパ・コロニーではそうではありません。人は資源衛星から運搬しなくても勝手に増えますから、優秀な機械よりよっぽど安価な場合が多いのです。
また話が逸れてしまいましたね。ご容赦ください。エレンは、とにかく色々なお話を知っていました。お母様が熱心な信仰者だったようで、大昔に神様とお話をされた偉い人の物語をすっかり暗記していたようです。
彼女の話によると、人の命はすべて等しい価値を持っていて、死んだ後、善い行いをした者だけが集められて、水も土も食料も酸素も有り余る、素晴らしい世界で暮らすのだと言います。ですから、人々はつまらないことで争ったりせず、頬を殴られても反対の頬を差し出してさらに殴らせ、相手の怒りを解きほぐすほど温和なのだそうです。
エレンは嬉しそうに、地球には信仰の仲間が百億人もいると言っていました。地球の半分もの人が私と同じ物を愛し、同じ物に愛されているのだと。私はそれを聞いて、地球というのはまさに彼女の言う楽園に違いないと思いました。地球のあなた様はエレンと同じ信仰の方ですか? そうであったらと願って止まないですが、違っていても構いません。エレンは信徒ではない私を愛してくれましたから、きっと、そんなことすら愛の前には関係が無いのです。
私たちはみな、給金の大半を貯蓄しています。祖母から母へ、母から子へ。貯めて貯めて継承するのです。私の家は7200Dの貯蓄がありました。四代かかって貯まったお金です。私の仕事は比較すると高給で、切り詰めれば年間で120Dほど貯蓄に回せます。地球へ向かう惑星間往還船号に搭乗するには2万Dほど必要ですから、私の家の――つまり、長姉の子や孫が生きているうちには一人、地球へ行くことができるのです。
私たちメガロパ・コロニーの一般住民の唯一の願いは、まさにそれでした。血を引く誰かが地球の地を踏めれば、一族の魂のすべてが慰められるのです。
しかし。エレンはお金を使うことに躊躇がありませんでした。肉を食べ、野菜を食べ、おしゃれをしていました。稼いで余ったお金は、いつか中古の宝石に変えるのだと言っていました。宝石なんて見たことはありませんでしたが、地球から来た石にどれだけの価値があるかなんて、考えるまでもありません。エレンには、いつか、それを手に入れる自分を想像するのが生きる糧だったのでした。
私は彼女のことが心配になりました。だってエレンは、昼食のたびに、私の給金じゃ節約しなくても手が届かないくらい美味しそうな食事をしていたのですから。
それでも彼女は余裕があるようでした。地球の人のような暮らしをすれば、魂が地球に近づくんじゃ無いかって、笑い話のように言っていました。一緒に食べないかといつも誘われたのですが、私はお金を自由にする勇気なんてありませんでしたから、いつも断っていました。それでも彼女は優しく、週に一度、私に栽培肉の半分を切り分けては、食べさせてくれました。それはもう疲れの全部が消え去るぐらい美味しくて、楽しく、そして美しい一瞬でした。
彼女はいつだって機嫌の良い人でした。どれだけ疲れていても楽しそうに笑い、優しく、完全な人でした。
でも、年に何日か、睡眠の時間が来ると、私の前でだけ、その細く美しい眉を歪めるのです。それから決まって、ここで死んだら、私はどうなるのかと言うのです。
死んだら、どうなるか。簡単な話です。持ち物はリサイクルされ、肉体は有機物回収槽で溶かされて培養肉や野菜になります。彼女が美味しいと食べているそれに、彼女自身もなるだけのことです。
私の言葉に、彼女は決まって「魂は?」と訊ねます。魂はどこに行くのかと。魂は永遠不変不滅だから、どろどろに融けたりしないのだと。これに私は困ってしまいました。なにしろ、学のない私には何を言うこともできませんから。
何度も聞かれたある日。「天国じゃないの?」私は彼女から教わった言葉を返しました。善い人々は死後、天の主の国に還るのだと彼女は言いましたから。でも、その言葉に彼女はまるで感電したみたいな表情をしました。それから、エウロパのように凍り付いた瞳で、暗闇でぎらりと光る瞳で「それじゃあダメ」だと言いました。
「ねぇ、その天国はどこにあると思う?」彼女が言います。彼女が言うヘブンが、私たちの言葉では「天」という意味だというのは知っていました。天というのはコンテナの上部を指す私たちの言葉でした。
上にあるんでしょう? 私が言うと、彼女は嬉しそうに、うっとりと、頷きました。「重力を振り切った先。私たちの身体の一片に至るまですべてが自由になる場所。それが天国。」暗闇に、まるで閃光のように言葉が生まれては、輝き、消えていきました。
「――私たちは、産まれる前から天国に居るのよ。」
エレンはついに、泣き出してしまいました。途切れ途切れ、まるで喉から鉄屑を吐き出すように痛々しく、彼女は言いました。
「母なる地球を離れて、重力を振り切って、もう宇宙塵と見分けもつかないぐらい遠くまで来て。それでも私たちは、全然自由になれていない。見えない重力に魂が磔にされているの。みんな地球なんて見たこともないのに、私たちの祖先が地球のどこで産まれたかで――何千年前の祖先が地球でどれだけ太陽に灼かれた程度のことで決まる皮膚の色だけで、いまだに魂にまで色を塗って優劣をつけてる。」
だから、どこにも行けないのだと。死んだ人間の魂がたどり着く場所なんてどこにも無いのだと。だったら、なんで私たちは産まれ、生きているのかと。
私はその言葉に強く反対しました。エレンは、私のことをちゃんと隣人として愛してくれましたから。エレンはその熱い身体で私を抱きしめて、しばらく泣き続けました。私は彼女の呼吸に合わせて息を吸いました。二つの心臓の鼓動がひとつに融けていくようでした。数分でしょうか。数時間でしょうか。わかりません。耳がすっかり静かに慣れたころです。「あなたのことを愛しているから、特別なの。赦して。ごめんなさい」罪過に震える声でエレンが言いました。しかし私は、その言葉の嬉しさに心臓をギュッと握り締められたことを覚えています。
画一な博愛より偏った特別な寵愛のほうが嬉しい。きっと、そんなことだから私たちは重力に絡め捕られてしまうのですね。喜びの紅が差した私の頬をみて、エレンはどれほど私のことを軽蔑したでしょう。
そんなことが在ってからもエレンは、私に本当に優しくしてくれました。色々なものを与え、教え、導いてくれました。彼女との日々は、私の全てでした。しかし、私は、何を返すこともできなかったのです。あぁ、なんと私は愚かな臆病者だったのでしょう。大赤斑が見えるとエレンが燥いだあの日。展望台で極光を見ようと強願まれたあの日。少し頭が痛いと言ったあの日。密航して地球へ行こうと誘われたあの日。仕事のことや家族のことなんて、全部棄ててしまったら良かったのです。地球の人。教えてください。もし私が地球の人間だったら、自由に生まれ、自由に死ぬことができる私だったら、私は彼女の気持ちに応えることができましたか? それとも、そんなことはなく、ただ私が臆病なことが悪いのでしょうか。どんな小さな声でも、どんな冷たい声でも構いません。どうか、どうか教えてください。
――ある、空気が少しだけ薄かった日のことです。
メガロパの筋繊維が肥大しているのだと工場主が言いました。成長期だろうとのことでした。成長期の繊維は歯ごたえが良く、地球で高値で売れますからみな殺気だった目をしていました。
にわかに内クチクラは大忙しになりました。この時期になるとメトロ用のトンネルのあちこちが肥大した筋肉で埋まり、男たちは掘削に駆り出されます。その流れで、私たちの休暇はなくなりました。第一業務時間で缶詰を作り、第二業務時間ではメガロパの筋繊維をフレークにする仕事をすることになりました。みんな移動のメトロのなかで眠るのが日課になりました。
フレークはご存知ですか? もちろんご存知ですよね。いま聞いてくださっている音声データを焼き付けたシートに包まれているシーフードミックスの筋繊維のことです。メガロパの全長は直径で2600キロありますから筋繊維といってもメトロの車両ほどあります。
それを切削機で切り出してコンベアで運び、幅でいうと200mはある巨大な破砕機でバラバラになるまで解したものです。
筋繊維を投入する仕事は大変な重労働ですから、それは幾人か残った男が担当していました。しかし人間ですから不眠不休で仕事をすることはできません。もう三日ほど仕事を続けていると言った担当者の男性が起き上がれなくなってしまい、私たちの誰かが投入係をすることになりました。
工場主は周囲を見渡して、私のことを呼びました。お前が適任だと、言うのです。私は嬉しくなりました。仕事が認められたような気がしたのです。
破砕機に続く階段を登ろうとしたとき。エレンが怒鳴る声がしました。普段、私に向けるのとは違う鋭い声でした。差別だ、危険な仕事を、公平に体力で選ぶように、だったら私が代わりに――私は愚鈍でしたが、断片的に聞こえるエレンの言葉から、さすがに状況がわかりました。思い上がりが恥ずかしくて、涙が出ました。私は班のなかでよっぽど腕の力があるのです。ですから、気にしないで良いと言うべきだったのです。でもどうしても言葉が音になりませんでした。破砕機の上から私を見つけたエレンが、寂しそうに、優しそうに、微笑みました。手を振っていた記憶もあります。私は涙を拭うのに忙しくて、それに応えることができませんでした。
代わりに、私に与えられた仕事は、コンテナにフレークを詰めることでした。いっぱいまで詰めたら、番号を書き込んでコンベアに載せるのです。これが私たちの缶詰工場に届くのだと思うと、まるで世界の仕組を曝いたような気までして痛快でした。でもそれは、本当はエレンがするはずだった仕事です。
手を動かしながら、私はエレンにどうやって謝ろうかなどと考えていました。第二勤務のおかげでお金に余裕ができましたから、食事にでも行こうと誘うことを思いつきました。いつものお礼をさせて欲しいと。
作業にも慣れた頃です。あと十五分程で休憩になるなと思ったことを覚えています。衛生手袋の人差し指の所に縫い付けてある無インクペンで、Lの1977ー1231とコンテナの行き先を感圧電子インク紙に書き写したときの事です。
悲鳴が聞こえました。
短く鋭い声。
悍ましい声でしたが、聞き間違えるはずもありません。それはエレンの声でした。私はすべてを投げ出して、破砕機の階段を駆け上がりました。階段が117段あったことだけが、なぜか記憶に焼き付いています。
階段を上った先の凄惨さは、言葉にすることができません。覗き込んだ粉砕筒のなかに反響する鈍く低い機械の声は、激しい暴力の音をしていました。みんな、エレンのことを助けようとしました。でも無駄です。機械を止める権限なんて私たちにはありませんから。
エレンと、それから砕かれた筋繊維は循環洗浄水を潜って、圧縮空気にゴミ取りをされて、熱い蒸気で火を通されて、ついには立派なフレークになりました。
エレンは苦しむことも、祈ることも、抗うこともできず、骨も肉も魂も、粉々になってしまいました。
私は泣いて、機械を止めるように言いました。無駄です。工場長にすら、その権利はありません。有機物回収槽にフレークを入れてくれるようにも頼みました。そうすれば彼女の魂だけでも取り返せるような気がしたのです。でも無駄です。この大量のフレークを廃棄したらどれだけの損害がでるかわかりませんから。見なかったことにする他、ありません。
私は嗚咽や罵声が漏れないよう、強く舌を噛みしめながら、仕事を続けました。誰にも、この仕事を奪わせたくなかったのです。そのために平気を装いました。
そうして作業をしていた私は、気付きました。コンベアに、エレンが、流れてきたのです。
いま吐き出されているフレークのなかにエレンが居るのです。――もちろん、比率で言ったらコップに塩の一粒を入れたような物です。それに寄生虫対策で徹底的に異物は取り除かれ、洗浄もされていますから、色も匂いも普通のフレークとなんら代わりありません。それでも私は直感的に、それがそうだと気付いたのです。
L1979ー0525。彼女の魂を納めたコンテナの名前を、私は泣きながら書き込みました。
もうお分かりでしょう? あぁ、親愛なる地球の人。いまあなたの目の前にあるそれが、L1979ー0525のフレークを使った缶詰のひとつなのです。私はエレンの死に装束の代わりに、この変色防止用の缶内隔離紙を折っているのです。有機物回収槽に入れる代わりに、缶詰のなかに彼女を詰めて弔っているのです。
あぁ、エレンは無事、地球にたどり着くことはできましたでしょうか? 地球の重力の一部になることができましたか? そしてこの声を聞いているあなたはどれだけ素晴らしい人でしょうか。教えてください。どれだけの人を救った人なのでしょう。地球のどれだけ素晴らしい所にお住みなのでしょうか。お医者さまですか? お大臣さまですか? 科学者さまですか? 私の愛した人は、どのような人の血肉になったのでしょう。私はそれが知りたくてたまらないのです。
――いいえ。違います。
ごめんなさい。そんなことはどうでも良いのです。
エレンはそんなことを気にする人ではありませんでしたから。もう充分なのです。私たちの細やかな願いはすでに叶ったのです。メガロパ・コロニーでは、冷たく暗い真空の宇宙では、私たちの悲鳴は誰にも届きませんでしたから。私の声が地球の空気を震わせ、地球に住むあなたの耳に触れ、そして揮発していくエレンの魂を慰めることができたのですから。いまの私にこれ以上の幸せなんてあろうはずがありません。
親愛なる地球のあなた。あぁ、なんと感謝をすれば良いのでしょう。考えもつきません。それでも、それでも、もし欠片でも私たちのことを憐れに思ってくださったなら、ほんの瞬き一度で良いのです。ほんの一吐で良いのです。ただ、ただ、憧れていた地球の一部になれたエレンのことを祝福してくださいませんか。
/3
全身が、汗だらけになっていた。
私は、その告白を、遮ることができなくて、ずっとそれを聞き続けていた。全身の筋肉が張り詰めていた。暴れ出したくなるような、何もかもを壊してしまいたくなるような、そんな衝動に包まれていた。
耳に突き刺さった言葉が、抜けない。
懐かしい声。知らない声。
ゆっくりと、缶詰に記された製造年月日を見る。
私が産まれるずっと前の日付。
異物騒動で価値が暴落するすこし前の日付。
母が密航者として地球に渡ってくる一年前の日付。
空気を吸う。
シーフードミックス缶の匂い。命の匂い。
喉が痺れていて、良かったと思う。
そうでなきゃ、私は何か汚い言葉を叫んでいただろう。
立ち上がる。
重力が、私の足を、心臓を、脳を、鷲づかみにする。
ゆっくりと、歩く。
自分の足じゃないみたいだ。
私は、壁に掛けられた母の遺骨のダイヤを掴む。それから、それを、堆く積まれた母の形見の缶詰の一つと、その蓋とで挟んだ。それに向かって、家の中にあるありとあらゆる重い物と堅い物を叩きつける。
安物の人造ダイヤは本物に比べると簡単に砕けるので注意が必要だ――なんて、福祉葬儀課の役人が言っていた、貧乏人には何の役にも立たない知恵が、役に立つこともあるものだ。
気付いたら、母のダイヤは、砂粒みたいになっていた。
机の上には、皿にあけられたシーフードミックス缶のフレークがひとつかみ。私は、砂粒みたいになった母のダイヤを――いや、葉山恵那の魂をエレンさんの魂に振りかけた。
「おかえりなさい。地球は良い所だよ」
私は二人の魂に嘘をついて、それを呑み込んだ。