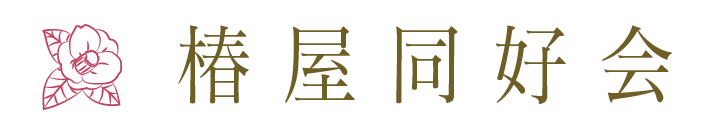――ああ。やはり、シネマとは人生だ。
初老の男、ニーノ・アバーテは、かび臭い合成繊維のチェアに腰を下ろしながら、そんなことを回顧していた。シネマには人生がある。人間がある。摂理がある。瑞々しく、生き生きとした、身の丈にあった命がある。それは何も、上映される作品に限ったことではない。決して高価ではない、一食分ぐらいの安いチケットを手に、箍を外さない範囲での非日常と芸術を味わおうとする庶民たち。生活と地続きの服を着て、生活の匂いをさせながら、バケツのようなコーラとポップコーンで映画を流し込むのだ。
そう。これが、人間だ。等身大という奴だ。だがしかし、それに引き換え――。ニーノは、自分のコンサートを見に来る上流階級どもの顔を思い出してため息をつく。使い方も思いつかない程に無粋に、過度な金をもち、怠け、無節操に浪費をする。あんなものは人間ではない。貪欲な豚だ。実用性のない高い服を着て、わかりもしない芸術を、ジャンクフードのように貪る奴ら。
まったくもって、不健康だ。
怒りで心拍がせり上がるのを感じたニーノは、咳払いをしてチェアにもたれ掛かる。酸化した皮脂の匂いが鼻腔をくすぐる。視線の先には小さなスクリーン。スピーカー用の穴があいていない、本物のスクリーンだったが、残念ながら今日の主役はこれではない。ニーノは、自分の座席の隣に手を伸ばす。そこには小さなアイウェアがひとつ。彼が仕事で使う物より二世代ほど新しい最先端の実験用デバイスだ。
――それを触りながら、ニーノはある男の名前を呟いた。
フィルム・スコアという形でこの業界に携わっていれば、いやでも名前を聞くあの犯罪者の……いや、旧友にして映画監督である男の名前だ。芸術への温度差からか、ともに仕事をしたことは終ぞ無かったが、それでも不思議な因果のようなものを、ニーノは感じていた。
だから、その手紙が届いたとき、ニーノは不思議と驚かなかった。その表現を見せたいと思ったのか、自分に何かを見せたかったのか、よく分からなかったが、手向けに応募ぐらいはしてやってもいいか、と、思ったのだった。
ニーノが物思いに耽っている間に、アイウェアがライフパス端末の情報を読み込んでいく。このカタツムリは、持ち主の人生を食べて、複雑怪奇な本物で、レプリカな、映画を吐き出す。代金と呼べるようなものは、それで充分らしい。――自分の詰まらない人生にどれほどの値打ちがあるものかとニーノは訝しがったが、買い手がそれで良いというのだから、売り手が萎縮する必要は無いと思い直す。
二度、三度、四度、スクリーンと手元と視線を行き来させる。手前も奥も、不満なく綺麗に見える。数ヶ月前までは加齢による経年劣化に不便を感じていたが、献体幹細胞による治療の効果ですっかり若い頃に戻ったようだった。良い買い物をしたな、とニーノは改めて思った。次は耳も手入れしてもらうことにしよう。
ニーノは、網膜投射型アイウェアが映し出す疑似スクリーンの位置を、ヤニで黄ばんだ本物のスクリーンに重なるようにキャリブレーションする。懐古的だな、と自嘲しながら、上映開始の疑似ボタンを押す。
やや間があってから、室内灯が完全に消えた。
仰々しく、上映を告げるブザーが鳴る。
音にあわせて、誰かが息を呑む気配を感じた。ニーノはそこで初めて、この映写室に自分以外の人間がいることに気づいたが、視線で追うのを辞める。そこにいる誰かが映画の登場人物だとして、それを先に見てしまうような無粋はしたくなかった。
――さぁ、誰も見たことが無い傑作映画を、初めてくれ。
ニーノは、スクリーンに向かって、小さくそう呟いた。
/1
最初に映ったのは見知った町並みだった。あちこちがゴミで汚された、見慣れたいつもの、歪んだ都会。ニーノが生まれ育ったこの都市は、オペラや名画や宝石や歴史でめいいっぱい着飾った街だったが、足下はこんなものだ。
その街並みを進む、一台の自動掃除機。街路清掃用のそれは、周囲をきょろきょろと小動物のように見回しながら、路上に落ちたゴミを小気味よく飲み込んでいく。
その自動掃除機に跨がっている指導係は、少年だった。油と埃にまみれた制帽を目深に被った彼の名前が、テロップで紹介される。ロウタと言うらしい。それはつまり、彼が主役ということだ。年の頃は十代前半といった所だろうが、栄養が足りていないのか、激務故か、体は小さく、頼りなかった。
その虱の集った服を見て、骨の浮き出るような指先を見て、はっきりとした意思の宿った双眸を見て、ニーノは胸をなで下ろした。
――当たりだ。彼はそう思った。これは、自分が見たかったシネマだという直感があった。安っぽい感動を大量生産するための商業フィルムではない。等身大の人間の擦り切れるような痛みを伝えてくれるシネマだという直感だ。
なにより、ロウタという名が良い。異国風の名前だったが、ニーノにとって、それはとても馴染みのある、敬愛する作曲家の家名と同じだったからだ。
「チャオ! マエストロ!」
通行人が、嘲るように自動掃除機とロウタに挨拶をする。だが、ロウタは嫌がるそぶりなど見せずに手を振り返すと、小さく息を吐いて、それから、大きく、息を吸った。
*****
瞬間。鳴り響く音。それはさながら鈍重な雷撃だった。
――ああ。こんな醜いマッシュアップが赦されて良いのか。ニーノは、危うくそう叫んでしまいそうだった。前席に括り付けてある超指向性スピーカーを手のひらで覆い隠し、苛立ちを隠さない顔で疑似スクリーンを睨め回す。
聞かなくても分かる。これは酷い演奏だ。
トッププロと呼ぶにはあまりにも醜いボウイング。不揃いな呼吸。乱れる音。そこには芸術などと呼べるものは存在していなかった。
ニーノは、苛立たしくため息をつく。
誰かが言った。人工知能は人から仕事を奪ったりはしないと。だが、それが齎したのがこの退屈な音楽の熱的死だ。民衆は人工知能がひとつひとつオーダーメイドで作った曲に夢中になった。人工知能は過労死もしないし、食事もしない。安い電気を食わせれば、ジャンクフードのような音楽を無限に吐き出し続ける。
トッププロは、良い。そこには音楽以外の付随したステータスがある。外国で大きな賞をとった巨匠(マエストロ)の曲を聴くという経験に価値があるのだから。
それが草の根を枯らし、トッププロの心を腐らせた。
客席は冷め切り、指揮者の落胆は顔に漏れている。
地獄だ。ここには芸術など無く。そして、芸術では無い何かを覆い隠すエンターテイメントという名の欺瞞すら無かった。
演奏が終わる。さっきまで退屈そうだった観客は顔を輝かせ、盛大な拍手をする。他人の拍手の残響を聞いて、自分が食った芸術の味が良かったのだと思い込む。
最悪だ。ニーノは、小さく呟く。
ステージの中央。取り繕った笑みで主席奏者と握手をする数日前のニーノ自身の姿が、そこにあった。
*****
誰かが言った。人工知能は人間から仕事を奪わないと。しかし、尊厳を奪わないとは言っていなかった。牙と爪を抜かれ、さらには剣も銃も棄てて久しい人間という獣は、忘れていたのだろう。尊厳というものは無から生まれるものではないということを。
機械は尊厳を求めない。動物と同じだ。では、尊厳を求めない存在より能力で劣る人間はどうやって生きれば良い? ――ニーノは、少年に自分を重ねていた。
自動掃除機は人間などいなくても充分に仕事を熟す。八十個ある二千万画素の瞳と、各種センサー技術がある。あらゆる物体のスキャン情報が入っている。二つしかなく光学情報しか認識できない不完全な眼と、一キロ弱しかない脆弱な脳の人間なんかよりよっぽど掃除に向いているのだ。 ……ではなぜ、そんなご立派な機械の上にロウタは乗っているのか? 簡単だ。機械は責任を取らないからだ。機械には罪の代償として剥奪される尊厳や生命が無い。頭を垂れようが、万の謝罪を口にしようが、自害してみせようが、それは唯のプログラムでしかない。
つまり。この見窄らしい少年は、この機械がヘマをした時に身代わりになるためにここにいて、その代償として幾ばくかの賃金を得ているのだ。
すっかり、この世界は地獄になってしまった。ニーノは後頭部を掻きむしる。安物の空調が遠くで唸る。産業革命が、馬力しか持っていない学も技術も無い労働者を乞食に堕としたのと同じように、人工知能は、特別な才能を持っていない人間から、人間としての尊厳をこんなにも残酷に剥ぎ取ってしまったのだ。
自動掃除機が体温の無い瞳で街を眺める。回転するブラシの音が、路面の状態に合わせて漸次的に変化する。等間隔に並ぶ石畳の隙間が、等間隔のリズムを生み出す。
――その灰色の音場に、一番初めに入ってきたのは小さな金属音だった。少年の安全靴の鉄板が、強化樹脂でできた自動掃除機の白い筐体を軽く打ち付ける音。
すれ違う女性が、それを見て微笑み、少年と機械に手を振る。ロウタは帽子に軽く手を当てて挨拶を返し、それから大きく息を吸い、咳払いをしてメロディを撫でた。
「深い歓びの高まりを感じるよ。まるで高貴な馬に乗った王様みたいに――」
懐かしい。ニーノは機嫌良く歌うロウタを見て微笑んだ。いつだったろう。彼が歌うのは、子供の頃に父に連れられて見たミュージカル映画の一場面の歌だった。
ニーノは、右手で中空を撫でて、音量を上げる。
ノブレス・オブリージュを高らかに歌うイギリスの銀行家の歌を、戯けた顔の貧しい労働者の少年が歌うというミスマッチもまた小気味よい。
やがて、歌が終わる。すれ違う男が拍手をした。それに気をよくしたのか、ロウタはステージ上の音楽家のような仰々しい挨拶をして、それから、次の歌を始めた。
/2
……重々しい無音が事務所を埋め尽くしていた。
画面の中のニーノは老いていたが、今に比べるとまだ少しばかり若かった。それだけで、ニーノは全てを察していた。そして、手に持ったデバイスを叩き割らなかった、あの日の自分のちっぽけな理性を褒めた。スタッフたちが見ている前で取り乱すのは、さすがに耐えがたい恥辱だ。
「先生、さっきのはいったい――」
「劇伴から降りてくれ、だそうだ」
「そんな……先生に落ち度は何も無いじゃないですか」
「私よりも売れるスコアを書く奴がいるらしい」
「そんな! あり得ない。あり得ないですよ。どこのどいつが――」
「ライフパス。新進気鋭の人工知能様だそうだよ。さすがの私も、観客全員の脳波を読み取って最適な音源をリアルタイムで生成するなんていう曲芸はできないからね」
激昂して、聞くに堪えないような言葉を吐き出す代わりに、ニーノは震える歯を誰にも悟られないように、そんな皮肉を吐く。
「そんな――そんなものは芸術じゃない」
「……君、芸術の定義は知っているかい?」
「人の心がこもった、人の心を動かす名作のことです。先生のスコアのような!」
「残念ながら、それは不正解だ」
飄々とした言葉は、ニーノ自身が、崩れそうになる自分に向けて説得をするために吐き出している物だった。
「芸術というのはね、こんなものは芸術じゃない、と言う呪詛とともに産まれるものだ。マルセル・デュシャンも、アンディ・ウォーホルも。ロダンだろうが、バッハだろうがモーツァルトだろうが、すべてがそうだ。芸術と世界との出会いは、みな、同じ拒絶と呪詛から始まる」
だから、人ならざる物が作った美しくない音楽も、次世代に評価されるべき芸術なのだから、と。自分が詰まらないスコアしか書けないから侮られたわけではないのだと。それは己の創作意欲に翳りを感じる老いた音楽家のちっぽけな自己防御のための言葉だった。
「人工知能なんて、無い時代に戻りたいです」
誰かが言った。
ニーノは、大いに頷きたかった。
だが、頷いてはいけないと思った。それは、牙と爪を捨て去る行為に他ならなかった。
「私が最後にアルバムを出したのは二十年前だ。もう絶版だがね。君は持っているかい?」
訊ねると、その青年は控えめに首を振った。それから、デバイスでは毎日聞いています。最高音質版を買っています、と続ける。ニーノは小さく微笑んだ。
「その音源は理論上、レコードより高音質らしい。もっとも年老いた私の耳ではよく分からないけれどね。だがまぁ、そんなものなんだよ。おかげで私はよく知らない遠い異国の音楽を聴いたりもできるし、この事務所の生計も、電子配信による物がほとんどだ。技術という物の恩恵ばかりを得るというのは些か、わがままという物だよ」
スクリーンの中のペテン師を眺める。
本当は、誰よりも技術の進化を憎んでいたくせに。
自分を老頭兒に堕とした全てを恨んでいたくせに。
「――さぁ、切り替えて、人にしかできない仕事をしよう」 そう言うと、周りのスタッフたちは意欲に満ちた雄叫びを上げた。単純だ。そう。身の程を知れるほど、音楽への才能が無い奴らは、単純で良い。羨ましいほどに。
今ではもう名前も覚えていないスタッフたちの顔を眺める。彼らは一体、何を見限り、何を諦めて去って行ったのだろうか。ニーノはそんなことを考えていた。
*****
場面が切り替わり、夕方になった。ロウタは街をぐるりと周り、そして街外れの小さな処理施設に戻ってきた。部屋のなかには小太りで無精髭の男が一人。この再処理施設の責任者、チッチであるとテロップで表示された。三十代半ばといった所だろうか。世間に対して飽きた人間特有の、どろりと零れ落ちそうな瞳をしていた。
「親方、戻りました」
ロウタが燻(くす)んだ声で挨拶をした。親方のチッチは面倒そうに顔を擡げ、仕事の首尾よりも安物のプロジェクタで映写された映画のほうが重要だとでも言いたげな表情で、「おう」とだけ返事をし、すぐにまた寝転がった。
ロウタは相棒の自動掃除機を駐機場に誘導させると、本体両側についている停止スイッチを押す。機械はまるで人間のように全身を弛緩させ、その円筒形の体の上部――無理矢理に人体に例えるのであれば、胸のあたりだろうか――にあるハッチを開放した。
「今日もお疲れ様」
強化プラスチックの頭部を二度、ノックするように叩くと、少年は上裸になり、躊躇なくそのハッチに腕を突っ込んで、レバーを引いた。機械は豪快な音を立てて、金属、プラスチック、生ゴミなどと材質毎に分別したゴミをそれぞれの廃棄孔に吐き出していく。
「ヴェガスから果てなく続く砂漠の道――」
ロウタは見事なアカペラで歌う。カフェを舞台にした古い映画の主題歌だ。ニーノは、その選曲の巧みさに小さく笑った。続く歌詞は「修理が必要なコーヒーマシンがあるの」だ。作業の辛さや過酷さをうまく笑いに転化している。
コンプレッサの振動音が歌を所々かき消してしまうが、それでも少年の歌の巧みさは判る。正確さはもちろん、所々に歌詞の持つ情熱や悲哀などの感情を反映させる感覚が良い。それはつまり、それほど感情を育てなければならないほどつらい暮らしを送ってきたということだろう。
「おぅい、ロウタ。どうせ歌うなら景気が良い奴にしろ」
工場(こうば)の奥から、眠そうな、低い無粋な声がする。ロウタは、返事の代わりに、歌を流行りのポップスに変える。「そうそう、それだよ」チッチは気分良くその旋律を乱雑になぞる。
歌いながらも、ロウタは相棒の体躯を布で拭う動きを止めたりはしない。洗浄用の薬品を使っているようだが、手袋などはつけず、素手のままだった。――環境保護の名目で、石油由来の使い捨て製品に大きな課税がされた余波だろう。金持ちの道楽の尻拭いをするのは、いつも食い詰めて尊厳を放棄した貧困者だ。
それからロウタは、自動掃除機の内部から排出しきれなかったゴミを嫌な顔一つせず、素手で摘まみ出して棄てて行く。
ひとしきり作業を終わらせたその足で工場のはずれまで行き、着ていた作業着を業務用の洗濯機に放り込むと、そのまま、ボイラーの排水を加水して適温にしたシャワーで全身の汚れを落とす。
ロッカーから取り出した私服は、作業着より幾段もボロボロで、ところどころ擦り切れていた。それに身を包むとロウタはチッチの元へ戻り、いくつかの事務連絡をする。チッチは気怠げにそれを聞くと、懐から数枚のコインを取り出して、渡した。
給料を現金で支払っている様子に、ニーノは驚きと同時に、ある疑いを感じていた。さまざまな理由――最大のそれは資金洗浄だ――から、政府によって事実上、禁止されているからだ。となると、見た目通りの、下手するとそれ以上に危うい工場かもしれないな、とニーノは思った。
そんなことも知らぬような晴れやかな顔で、ロウタは給金を受け取ると、そのまま夕方の街へ駆けだしていった。
/3
あくまで、ニーノ・アバーテの個人的な観測だったが、芸術というのはどうやら、根から腐っていくらしい。花や実は利用価値が少なからずあるから、根が朽ちても生き残ってしまうこともある。
――そういう意味で、自分の「花や実」というのは作品そのものではなく、その経歴と受賞歴にあったのだと、ニーノは理解してしまった。持っていた端末を落としてしまいそうなほど、怒りと恐怖で手が震えていた。
「それはつまり、私に人工知能のゴーストをやれと?」
久しぶりに来た大口の案件だった。予算も申し分ない。なかなか大作の映画だ。以前だったら断っただろうが、いまだったら気分良く引き受けてやろう。そう思っていたニーノだったが、それら全てを叩き潰されるような条件を、先ほど聞いてしまったのだ。
「いえ、ですから、先生のスコアをすべて学習させ、そこから最適な新しい旋律を機械に書いてもらうということです。ですから完成品は先生の作品が持つ良さを引き継いでおりますし、ファンのかたも喜んでいただけると思います」
――なんだそれは?
目が霞むのは老化のせいだけでは無いだろう。
死んだアーティストの作品を機械に学習させて、尊厳も芸術も全てを冒涜させて金儲けの手段に使う奴らがいるということは、ニーノも知っていた。だがそれは、「手に入らない物を無理矢理に産み出す行為」なのだと思っていた。
だが。ニーノ・アバーテは、ここに健在なのだ。
「私が書くと言っているのだが?」
「いやぁ……それは……」
声に混じる侮蔑の色。それはつまり、作曲家としてのニーノ・アバーテは不要だということだ。機械のほうが、よっぽど有用だと。機械にその名前を明け渡せ、と。
気が狂いそうだった。
今の、老いぼれて、発想も枯れ果てた自分だけではない。かつての自分までが陵辱されているような、そんな屈辱だった。自分はいままで、誰に向かって音楽を創り、奏でて来たのか。誰一人として、自分の音楽に向き合ってくれていなかったのではないか。そんなことさえ思っていた。
「独占契約をしてくれればその倍をお支払いします。どうですか? 先生は二度と楽譜を書くなんて無様な労働はせず、遊んで貴族のように暮らしていけるんです」
舌が痺れる。肚が震える。
息の吸い方も、唇の動かし方も、英語の喋り方も、全てを忘れてしまったようだった。
断れ、と、本能が叫んでいた。
金のために楽譜を書いたことなんて一度も無い。自分はただ、芸術作品を創るためだけに今まで――
「先生のスタッフの……ええと、リベルトさんでしたっけ? 結婚されて、お子様も産まれるそうですね。どうでしょう。師匠として家や車のひとつでもプレゼントするというのは。我々は、先生さえその気なら、スタッフみなさんの生活を完全にサポートする準備がありますよ」
二枚舌の悪魔がそう言った。
ニーノは、声にならない唸り声を上げた。
*****
ロウタの家は、まるで独房だった。短辺方向には寝転がることもできなさそうな狭さで。寝返りをしたら落ちてしまいそうなベッドと、何に使うのか判らない小さな棚だけがある、行き止まりのような場所だったが、ヒビの入った小さな窓硝子からは、青白い星がジラジラと光っていた。
「ただいま」
少年は居ない誰かに小さく挨拶をして、ベッドの上に座る。立てかけてある小さな写真を撫でて、それから、その下にある硝子の瓶を取り出した。
瓶のなかには薄汚れた硬貨がいくらか詰まっていた。おそらく、彼にとっての全財産なのだろう。
瓶の八部目のあたりには硬貨で削った白い二本線があった。彼が持ち帰った硬貨をその中に入れて蓋をしめ、ぐるぐると眺めると、星明かりがその線に反射して小さく光った。
寝転がったロウタは、懐から小さなパンを二つ取り出した。廃棄寸前の乾燥したそれと、いくつかの栄養補助錠が彼の夕食だった。帰りの道すがらに買ってきた物だ。予算にはまだまだ余裕があるように見えたが、彼は一日の給金のほとんどを瓶の貯金に回しているのだろう。
寝転がったまま、見上げると、そこには小さく切り取られた星月夜がある。彼の心は、それだけで満ちたのだろう。とても楽しそうな、嬉しそうな顔をした。年相応の子供の顔だった。
「――」
響いてきたのは、歌だった。歌詞は無く、聞き覚えの無い曲だったが、不思議と情景が伝わってくる。遠く輝く星への渇望。重力に縛られた自分への慰め。
澄み切った歌声は夜空に響いて、ゆっくりと熔け落ちていく。呼応するように極星が燦めき、世界は彼に赦しを与える。
ニーノは、その歌声に心の全てをすっかり奪われてしまった。
/4
ロウタの仕事は毎日続いた。
雨の日も、酷暑の日も、いつかの終戦を祝う日も、ファシストたちの演説があった日も、少年と自動掃除機はただただ平凡に、地道に、いつもと変わらず、街を掃除して回った。
そういえば一度、自分も嘯いたことがあったな、とニーノは思い返していた。清掃人の雇用を守るためなのだから、街を汚すことは納税者の責務だと。
ロウタの仕事はニーノの眼には過酷なそれに映ったが、
逆に、街が清潔であれば、過酷な仕事でなければ、少年に賃金を支払って自動掃除機を動かそうという意思も無くなるだろう。それが、良い事なのか悪い事なのか、判別など付かなかった。
ロウタは、歌う。
彼は驚くべきことに、毎回、毎回、その場、その時、その聴衆に合わせて選曲をしていた。そこには深い泉のような教養の輝きがあったし、自分の技巧を見せびらかすのではなく聴衆を楽しませたいという強い意志を感じた。
それは反抗であり、凱歌なのだと、ニーノにはわかった。ニーノにだけは、わかったのだ。魂を売り渡して生活をしている人間であり、魂よりも高貴な感情に突き動かされて生きてきた人間同志だったから、通じる物があったのだ。
歌声が街に響き渡る。その間だけ、彼は機械の隷属ではなく、一人の歌手だった。瞳に意志の火が灯り、尊厳を取り戻す。
拍手をする者。ともに歌う者。小銭を投げる者。アイウェアでその様子を撮影する者。行き交う人たちもみな、汚らしい服を着た、虱の集った、酷い臭気の、貧しい少年に対して、尊敬に近い表情を向けていた。
あぁ。懐かしい。ニーノは深い渇望を抱きながら、その姿を食い入るように眺めていた。網膜に焼き付けるように。鼓膜に刻み込むように。
――それは、音楽を手放した彼自身には、羨むことすらできない、とても眩い光景だった。
*****
「煩いな。私は純音楽家なんだ。劇伴は遊びなんだよ」
思えば、若い頃からそうだった。
ニーノは、スクリーンに映った若い自分を見て、眉に深い皺の峡谷を作った。「吠える犬は咬めない」とはよく言ったものた。音楽のなんたるかなんて一握りすら掴んでいなかった頃、ニーノは良くそんなことを言って顰蹙を買っていた。
――その言葉すらも、借り物だ。
自嘲気味に、そんなことを呟く。敬愛する、そして自分と同じ名を持つ偉大な作曲家が、かつてこの国に居た。自分とは違って彼はオラトリオもオペラも熟し、アメリカに渡って映画音楽の大家になった。自分も彼みたいになりたいと思い上がって、その言葉や思想を真似ていただけ。
思い返せば、自分は借り物でしか音楽を作れなかった。それが巧かったから、誰にも気づかれないぐらいに巧みだったから、短い間だが、名誉と仕事にありつけたのだ。
それはつまり、ニーノ・アバーテのすべては、人工知能の劣化品でしかないということだ。無から芸術を作ることなどできないのなら、機械学習と何が違うというのか。
「そう言わずに。あなたは巨匠なんだ。あなたにしか頼めないフィルムがある。一緒に世界を狙おう」
真剣な顔で配給会社の男が言う。その言葉に、偽りは無かったな、と、ニーノは、その男の顔を眺めながら苦々しく微笑んだ。
泣きながら映画音楽について語る男に心を動かされた若い自分が、その手を堅く握りしめる。その手を取ったことは正解だったのだろうと、思う。あの瞬間、確かに自分には勢いがあって、情熱があって、そのフィルムは世界各地で大きな賞を取った。敬愛する同じ名の音楽家と同じ賞も取った。
配給会社のその男のことを、その後、盟友だと思ったこともあった。彼だけが自分の才能を見抜き、自分に育てるべき種を与えてくれる存在だと――結局、分不相応の評価が燃え上がらせた自分の傲慢が、彼との縁を焼き切ってしまったわけだが。
「なぁ、契約する前に、一つだけ聞かせてくれ」
若いニーノが、問うた。
「音楽は、芸術は何のためにある?」
ニーノは、胸ぐらを捕まれたような気がした。
答えなど、とうに摩耗して持ち合わせていなかったからだ。
かつて盟友だった、そしてフィルムの中ではこれから盟友になるはずの男が、偽りの無い眼で応えた。
「星や月みたいなもんだよ。――太陽が自分を照らしてくれない辛くて寂しい時に、自分が間違っていないことを、静かに教えてくれるのが芸術だ」
*****
自動掃除機は、中央広場の隅にある駐機場に停まった。ロウタが、社名の書かれたカードを駐機場のポールに翳すと、鈍い振動音と同時に充電開始を告げる電子音が鳴った。
週に一回、水曜日の巡回コースは普段のそれより長いようで、途中で三十分ほどの急速充電を必要とする。その束の間の時間だけが、ロウタにとって数少ない自由な時間だった。
ロウタは真冬の共有水道で念入りに手を洗うと、それから髪と顔を念入りに洗い、擦り切れそうな布で赤くなるまで水気を拭った。
それから服や帽子についた埃をはたき落とすと、広場外周沿いにある小さな店まで歩いて行く。それは、音楽屋だった。ニーノが若かったころはまだCDやレコードを買う人も多く、日用品の店という感じだったが、電子配信の隆盛におされて、すっかり骨董屋に落ちてしまった。
「――なんだ。また冷やかしか。小僧」
店主は、露骨に嫌そうな声を出した。それもそうだ。いまやCDやレコードは稀少品。流通数は少なく、買うのは好事家ばかりだから、値段は高く、とてもロウタに手がでる金額とは思えなかった。
「ごめんなさい。見てもいいですか?」
「好きにしろ。盗んだりはしてくれるなよ」
「もちろんです! せっかくの音楽をそんな……」
「んなことは解ってるよ。ほら、早く見ろ」
ロウタは、ぺこぺこと頭を下げると、それから店に並んでいるCDを見て回った。ある棚を見ては悲しそうに顔をさげ、ある棚を見ては嬉しそうに眉を上げ、3枚ほどのCDを手に取ると、カウンターに急いだ。
「あの――」
「しょうがねぇなぁ」
店主は指を三本立てた。ロウタは飛び上がりそうに喜んで、ありがとうございますと言うと、ポケットから三枚のコインを出した。――夕食のパンと同じぐらいの金額だ。
「ほらよ」
店主は、自分の後ろにあるCDプレーヤーに、渡されたCDの一枚を入れる。真空管のアンプがすっかり温まっていることから考えるに、最初から聞かせてやるつもりだったのだろう。
「座れ。音楽を聴くんだ。集中しろ」
「はい。すみません」
ロウタは、差し出された木の椅子に座る。一瞬の緊張感を、艶のある低音が弾く。豊かに調和の取れた哀愁のある音が空気を震わせる。
エンニオ・モリコーネのシネマ・パラディソだった。悲しさと美しさと歓びが融けあった、人生そのもののような旋律。――なんと美しいことか。ニーノは無意識で、まるでロウタがそうしているように、身を乗り出して聞いていた。
至福の時はたった二分二十六秒で終わってしまう。店主はロウタに向かってにやりと笑いかけると、そのままディスクを取り替えて、次の曲を流し始めた。
アラン・シルヴェストリの「フォレスト・ガンプ」、フランシス・レイの「ある愛の詩」。どれもが映画を、そしてその時代に生きた人を支えた珠玉の名曲たちだ。
ニーノは、ロウタの選曲の良さに気を良くしていた。
やがて、三曲目も終わる。店主もロウタも薄らと涙ぐんでさえ居た。さぁ、次の曲を聴かせてやろうと店主が立ち上がった所で、ロウタの持つ仕事用の端末が安い電子音を立て、充電が終わったことを告げた。
「あの、もう行かなくちゃ」
「なんだ。また冷やかしか」
「……ごめんなさい」
店主は、名残惜しそうに真空管の電源を落としながら笑った。その微笑みの意味が分からなくて、ロウタは言葉を飲み込む。それでも、聞きたいことがあったのだと強く息を吸った。
「あの、すみません、探しているCDが在るんです」
ロウタが、店主に向かって何かを言った。小さな声だったからか、ニーノにはそれを聞き取ることはできなかったが、大方、作品名か作曲家の名前を告げたのだろう。
「さぁなぁ。盤が出ているんだか出てないんだか……。曲自体は聞いたことはあるんだが、どうだかなぁ。どうしてまた?」
「母が生きていたころ、二人で映画を見たんです。一回だけ。それが忘れられなくて――」
「そうか。気が向いたら、探してやるよ」
「ありがとうございます」
「わかったわかった。ちゃんと金、貯めとけよ」
「――はい」
ロウタが、元気よく店を飛び出していった。
店主は、彼が視聴の代金として支払った硬貨三枚を、レジではなく小さな貯金箱に丁寧にしまった。
/5
悪魔に魂を売り渡した結果は、あまりに呆気ない物だった。端末を握りしめ、項垂れる、いつかのニーノ・アバーテを、彼は鼻を歪ませて疑似スクリーン越しに眺める。
この時のことは、鮮明に覚えている。電話越しに、男は「私たちの作品が賞を取りましたよ」と言った。ニーノは数度、「あれはあなたの作品だ」と返したが、まるで言質を取るように執念深く「私たちの」と言うのでそれを受け入れざるを得なかった。頷いた時に首に流れた汗の感覚が、まだ真新しい嫌悪感を持って残っていた。
商業的結果を持って言うならば、人工知能は非常に優秀だった。非常に優秀に、ニーノの手癖を真似、大衆の好みに沿ってそれを捻じ曲げ、とても耳心地の良いジャンクフードのような音楽を、ニーノ・アバーテの名前をもって世界に届けた。
画面の中のニーノが、端末の電源を切って、革のソファに沈み込んだ。もっと上等な人生を送っていたら、きっとここで涙の一つでも流していたのだろうが、漏れ出たのは乾いた笑いと、世界への侮蔑の感情だった。
「そう、ですか」
報告を聞いたスタッフたちの表情は様々だった。自分たちの生活が安定するだろうことに喜んでいる者もいれば、世界か、ニーノか、あるいはその両方に失望した顔を向ける者も居た。ニーノには、そのすべてが自分の顔から剥がれ落ちた表情のように思えた。
「なぁ、私はどうしたら良いと思う」
虚空に向かって言葉が吐き出される。スタッフたちは皆、採点を告げられる直前の生徒のような表情をするばかりだった。だが、男にはそれを諫めることはできなかった。自分も同じだったからだ。いまさらながらに心を塗りつぶす悔恨と罪悪感に、神聖な物を冒涜してしまった自覚に、そしてもうどこにも戻ることができないことに、男は酷く、怯えていた。
「誰か、答えてくれ……」
誰かが判ってくれると、そんな風に期待していたのかもしれない。熱心な音楽愛好家になら、耳の肥えた評論家になら、世界的な賞の審査員になら――きっと誰かが、賤しくも金のために人工知能という悪魔に魂を売った最低の音楽家だと、糾弾してくれるはずだと。
だが、現実はどうだ?
今なら、わかる。かつての愚かな自分が映るスクリーンを眺めながら、ニーノは吐き捨てるように呟いた。
「音楽なんて、棄ててしまえば楽になる」
*****
「なぁ、おい。これはどういうつもりだ?」
ロウタは、視線を逸らして黙るしかできなかった。親方の足は、苛立ちを隠しもせずに、荒々しく揺れる。一日の巡回を済ませて工場に戻ったロウタを待っていたのはいつもの物臭な返事ではなく、鋭い裂帛の怒号だった。
駐機もそこそこに駆けつけたロウタが見たのは、ネットに投稿された、自分が仕事中に歌を歌っている動画だった。
「俺は、目立つなとお前に言ったな?」
ロウタは小さく頷く。チッチは仕事にあまり熱心ではない男だが、それは他人に求める仕事に対しても同じだった。目立たず、ただ体裁を整えればそれで良い。六割を淡々と熟してくれればそれで良いというのが、彼の信条だった。
だから、職務中に歌っていたことを叱責しているのではない。彼はただ、分不相応に目立って、注目されてしまったことに腹を立てていたのだ。
「ドブネズミにはドブネズミの生き方がある。いいか? あいつらは俺たちのことを何も見ちゃいない。何色の血が流れているのか、何を食っているのか、どんな尊厳を持っているのか。そんなものはどうでもいい。あいつらが見ているのは、その薄汚いツラと、虱だらけの制服だけだ」
耳目が集まれば集まるほど、そこに偏見という澱が溜まる。それは自分たちのような底辺層にとっては致命的な毒なのだと、チッチは言った。
「――そんなことは」
無い、と、ロウタは言いたかったのだろうが、途中でギロリと朽ちかけた眼で睨めつけられて黙ってしまった。ロウタは、誇りを持っていた。自分の歌で、人を楽しませているのだという誇りがあった。
「見せるつもりは無かったんだが」
そう前置きしてから、チッチはロウタにデバイスを手渡し、「読んでみろ」と言った。そこに並んでいる動画に対してのコメントにロウタは眼を通す。そこには、身なりを笑う罵詈雑言の言葉。それから、まるで犬や猫が必死に芸をやる様子を褒めているかのような、侮蔑に満ちた称賛の声。それから、見るに堪えない言葉の濁流があった。
「……な? これでわかるだろ?」
「――。」
顔を真っ赤にして、ロウタは必死に涙を抑える。声を出したらどうにかなってしまいそうだった。
「お前が住んでいるマンションの管理人からもクレームが来てる。良いか? もう、二度と歌うな。芸術なんてもんは、金持ちの道楽でしかないんだ。な? いい加減、わかっただろ?」
ロウタは、震えながら、小さく頷いた。
チッチは、その頭を軽く叩くと、「この前の歌の駄賃だ」と戯けた声で言うと、いつもの二倍の量の硬貨を、その頭の上に置いた。
*****
少年は、星月夜を見ていなかった。
孤独な――僅かに残った尊厳さえも奪われた帰り道は一際、昏く、色褪せていた。足取りはとても重く、その軽い体をなんとか引きずって川沿いを歩いていた。
握りしめた硬貨をパンに変えることもせず、帽子を目深に被ったまま、ただただ、街の喧騒から逃げるように歩く。
肺が鳴き、喉が震え、小さな音が漏れる。それは歌というにはあまりにも弱々しかった。暗闇に燐寸で火を灯すような音。止まりそうな足を、止めたくなる鼓動を、なんとか動かすための自傷のような音。
それが、ゆっくりと、朽ち果てるように、止まる。
辿り着いたのは、高架下。そこには街の灯りも星の光も届かない、真っ暗闇な世界。暗闇をずっと歩いていたロウタの眼にも、何も見えないほどの静かな夜の吹きだまり。
何にも照らされない、何にも曝されない。
「世界が、こんな夜ばかりなら良いのに」
ロウタの呟きに、ニーノは思わず頷いた。
それは、音だけの世界だった。
誰が作った、誰が歌った、そんな物が熔け落ちていく世界。そこでは階層も人種も性別も曖昧で、ただ、単純に、吐き出される音の美しさだけが全てになる。
もし、自分の名前をすべて焼き捨てたなら、そんな世界に行けるだろうか。棄ててしまった音楽を、もう一度、拾い集めることができるだろうか。そんなことを、虚しく考えていた。
ロウタは、何度も何度も丁寧に、周囲の無人を確かめると、大きく息を吸う。
夜を震わせたのは、旋律だった。たった今、この少年の悲しみを消化して産み出された音の連なりだった。初めて聞く旋律だったが、ニーノはそこに不思議な懐かしさを感じていた。まるで、自分の心臓を直接震わせているかのような旋律だった。とてもスクリーン越しとは思えないほどの一体感が、ニーノにはあった。
歌声は、縦横無尽に夜を泳ぐ。誰にも邪魔されないように、浮かんでは消えていく様々な感情が星図のように紡がれていく。
歌詞は無く、表情も見えない。
ニーノは、ロウタの願いを叶えるように、知りすぎてしまった彼の全てを記憶の端に追いやっていく。記憶のなかの雑味が、その音楽に光を落としてしまわないように。
紡がれる旋律は、すべてだった。美しくも、醜くも、寂しくも、激しくも、弱々しくも、拙くも、巧みでもあった。すべての感情が、感覚が、調和し、ぶつかり合い、濁りながら澄んでいた。
それは宵闇のように真っ暗で、透明だった。
ニーノは、夢中だった。夢中で、存在しない鍵盤を叩き、その歌声に伴奏をつけていく。この旋律を、この歌声を、
包み込むにはどんな音楽が必要になるのか。不思議なほど軽やかに楽譜が編み上がっていく。
それは、長く、忘れていた感情だった。スポットライトに眼が眩んで、見えなくなっていた感情だった。
この煌めきこそが、芸術だ。
この寂しいほど儚い瞬きだけが、芸術だったんだ。
ニーノは、音楽を台無しにしないように小さな声で、ありがとう、ありがとう、と、何度も呟いていた。
二人きりの――一人と、一人の、決して混ざり合わないセッションは、それから一時間ほど続いた。
/6
無人になった事務所で、ニーノは久しぶりにワインを開けた。音楽家としての初めての給金で買った、その年の地元のワインだ。それを飲みながら郷愁を感じたことが驚きだった。自分にまだ故郷への想いが残っていたのが意外だったのだ。
仕事を辞めようと思うと告げたとき、スタッフの皆は一様にホッとした表情をした。いうなれば、長い放浪生活の末に逮捕された逃亡犯のような、そういう表情だった。
表向きは、音楽制作に専念するための隠遁生活ということになっているが、実態は違う。名と座とを人工知能に明け渡し、その実が擦り切れるまで幾許かの泡銭を受け取る余生を送るという意味だ。買える酒の品質は向上したが、酒の味は格段に不味くなった。差し引きゼロなら、上等な物だと思わなくも無い。
誠実に音楽を続けていきたいと言ったスタッフにも、人工知能ビジネスに乗っかって稼いでいきたいと言ったスタッフにも、音楽を辞めて真っ当に生きたいと言ったスタッフにもそれぞれ渡りをつけてやった。沈むニーノ・アバーテという名の船に残ったのは自分一人だ。久しぶりに身軽になって少しばかり、気分が良かった。
先方から命じられた最後の仕事は、人工知能が考えたアルバムタイトルをペンで走り書きすること――デジタルジャケットのタイトルロゴに使うらしい――と、引退を冠したコンサートツアーの仕事だった。
書いてもいない、聴いたこともない、自分の名義の「稀代の名曲」とやらを何回も聞き直しては叩き込み、メトロノームの代わりを務めるというのが、自分の音楽家としての最期らしい。音楽を裏切った音楽家としては、お似合いの末路だと思った。
気持ちは、凪いでいた。何を言われても、何をさせられても、全く気持ちが動かないから、何も辛くない。
「あぁ、やっぱり、音楽を棄ててしまえば良かったのか」
今までの悩みを全て捨て去った顔でそう言うと、ニーノはワインを煽り、グラスを壁に叩きつけた。
*****
それからのロウタの日々は、灰色だった。
トーキーの白黒映画だと錯覚してしまいそうなほど、彩りの無い、無音の日々が続いた。自動掃除機がゴミを収集する様子を「眺める」ばかりの日々は、ただただ惨めに少年の心を絞め殺していった。
ロウタは、言いつけを守るようにではなく、ただただ、あの夜を最後に、情熱が剥落してしまったように、歌うことを辞めてしまった。
歌うことを辞めたら、不思議と、一日の労働時間が短くなったようだった。あっという間に日が暮れて、なににも煩わされることもなく、労働が終わる。
「なぁ、ロウタ、ちゃんと食ってるか?」
流石に心配になったチッチが様子を訊ねるが、ロウタは曖昧な笑みを浮かべるだけだった。何か言葉を掛けようかと逡巡しているうちに、ロウタは水が流れるようにするりと工場を抜け出して帰ってしまう。
日銭を稼ぎ、それを瓶に貯め、浅い呼吸をし、眠る日々。人生を切り売りして、貯金の嵩に替えていく日々。それでも、瓶の肩のあたりに刻んである白い線を――目標金額の線を撫でているときだけ、少年は笑顔になる。それは、朗々と歌い上げているときと同じ笑顔だった。
水曜日の「余分な出費」が無くなったからか、瓶の中身は以前よりも少しだけ早く溜まっていく。
――労働と極度の節制の対価としては些か遅すぎる歩みが、ようやく、白い線に届いたその翌日の、ある冬の朝のことだった。
街は冷え込み、雪に覆われていた。自動掃除機の高性能なゴム製のトラックベルトが、いま思えば少し、経年劣化していたのかもしれない。もしくは、石畳のどこかが欠けていたのかもしれない。あるいはバランス装置の調整が悪かったのかもしれない。
それは、一瞬の出来事だった。
段差を乗り越えようとした自動掃除機が、転倒してしまったのだ。近くには大人しそうな老婆が一人。――慌てて避けようとしたのだろう。バランスを崩し、派手に転んでしまった。
自動掃除機の倒れる轟音と、悲鳴。
周囲の視線が、注がれる。
ロウタは、慌てて、倒れた老婆に駆け寄った。分厚い人工毛皮のコートが幸いしてか、体や頭に特に怪我があるようには見えなかった。足は、もしかしたら折れているかもしれない。少なくても、歩けるようではなかった。
ロウタは、自動掃除機から救急を呼ぼうとしたが、緊急停止状態になっていて駄目だったから周囲に呼びかけた。「すみません、端末を持っていなくて。誰か、救急に連絡をお願いします。誰か」
体を痛めた老婆に対して、親切な人は多い。すぐに数人が名乗り出て、さまざまな場所に適切な連絡をしてくれた。大きな病院がすぐ近くにあることも幸いし、救急車はすぐに到着し、その頃には落ち着きを取り戻していた老婆はいくつかの簡単な会話をしながら車の中に運ばれていった。
そこで、ロウタは端末が落ちているのに気づいた。
転んだときに老婆が落としたのだろう。
それを掴み取ると、いままさに出発せんとしていた車両の運転席まで駆け寄り、運転手にそれを渡した。
実時間にして、十時間ぐらい経過しただろうか。ロウタが工場に戻ったのは、すっかり夜になってからだった。あの後、入れ替わりでやってきた警察に事故の様子を説明していたので遅くなったのだ。警察が言うには偶発的で、かつ老婆に大きな怪我もなく、老婆もロウタの献身的な態度に大きく感動していることから、事件化せずに解決しそうだ、とのことだった。
自動掃除機(パサーレ)は外装にいくつか大きな傷が付いたが、特に故障などはなく、親切な警察官の手伝いもあって、自力で起こして、こうやって連れて帰ることもできた。
大変なことになったが、それでも何とかなって良かったと、ロウタが安堵の声を出そうとしたその時だった。
不意に、視界が覆われ、揺れた。ロウタは、気づいたときには工場の床に寝転がり、ぼたぼたと、鼻血を垂れ流していた。頭上から、雷のようなチッチの声が降り注いだ。
「てめぇ、何をしやがった!」
痛みで停止した思考が、ゆっくりと、戻ってくる。ロウタはチッチが間違った情報に勘違いしているのだろうと思って口を開こうとした。
「なぁ、なんで盗みなんてやった?」
「――盗み? そんなこと」
言葉の途中で、もう一度、殴られた。蹲って呻いているロウタを、チッチは乱暴に引きずり、そのポケットを改める。貰い物の板ガムがあるぐらいで、めぼしい物は何も無かった。
チッチは、自動掃除機の蓋を乱暴にあけ、その中身を探す。しかし、そこにあるのは当然、路上のゴミばかり。
「盗んだデバイスはどこだ! どこに隠した」
小さく浅い息を繰り返すロウタには、その言葉の意味がわからなかった。錯乱状態に近いチッチは、何度も何度も自動掃除機の中身を確かめたり、ロウタの持ち物を改めたりしている。
「盗んでなんか、いません」
「だったら、この映像は」
荒々しく手渡された端末の映像は、あの事故の直後の映像だった。老婆が落とした端末を、駆け寄ったロウタが掴みあげている――。
「この映像が証拠だと、このクソババァがうちに来やがった。足が折れたのは神の定めと受け入れますが、盗みを赦すことはできません、だとよ」
「そんな……このすぐ後に、ちゃんと運転手の人に」
その言葉に、チッチは、全てを理解したようだった。突発的に盗みを働くことは誰にでもできることだが、嘘をつくのには才能が要る。汚い世界と接点を持つ人間だったら、みんな思うことだ。そして、目の前の不器用な少年にその才覚がないことも、誰にだってわかる。
「あぁ! くそが」
チッチは大声で叫ぶと、自動掃除機を蹴り倒し、そのまま、工場の床に坐りこんだ。チッチは、憎んでいるようだった。あの老婆に詐欺師の才能を見抜けなかった自分と、古典的な詐欺にまんまと騙されたお人好しのことを。
「……俺は、目立つなと言ったよな。目立つと、こうなるからだ。親切心で物を拾っても、身なりが汚ければ泥棒だと思われる。心配して声をかけても乞食だと思われる。それから、目立つと、本当に悪い奴に眼をつけられるんだよ」
本当に悪い奴、というのは標的を選ぶのが巧い。それは、一部始終を眺めていたニーノも同感だった。日和見の人間がどちらの味方につくか、よく理解しているのだ。十人に聞いたら八人が、あの人は善い人だと言うような狡猾な悪人。――そういう奴に目をつけられたら、抗うのは難しい。
「目立った時点で、疑われた時点で、俺たちはもうおしまいなんだよ……」
そう言い終わると、チッチは怒声をあげて、スパナを壁に投げつける。その音に驚いて視線をあげたロウタは、初めて気づいた。工場に、一切の設備が無くなっていることを。三台あった自動掃除機も、自分の愛機しか残っていないことを。
「大切な家族写真が入っていたんだそうだ。戻ってこないなら、このまま書類をまとめて、商会を相手取って裁判をすると言っていた。そうなったら俺たちはネズミの餌だ。手元に物が無い以上、金で解決するしかない。……で、このザマだ。今日の分の燃料代すら払えない」
寝転がって、チッチは言う。必死に積み上げてきた仕事の上がりがこれなのかという絶望は、ニーノにも、とても馴染みがあった。
「なぁ、知ってるか? 献体幹細胞治療ってのがあってな。俺たちの一生分の稼ぎでも足りないような値段のクソ医療だ。それにゃ、ガキの細胞が使えるらしくてな。お前のクソみてぇな両目を売れば、ちょっとした家が建つらしい。 ――そんな死に方、嫌だろ?」
献体幹細胞治療、という言葉に背筋が冷たくなった。それは、ニーノが見ないようにしていた、金という物の負の側面だ。金で自由を買う人間がいるということは、金で自由を売る人間がいるということ。そしてその交換は不可逆だということだ。
チッチは、煙草を吹かしてから、気怠げに言った。
「大家に聞いたよ。金を貯めてるんだって? いくらだ」
ロウタは、反射的に立ち上がり、嫌だ、と叫んだ。
「死ぬよりゃいいだろ。そうすりゃ燃料代にはなる。掃除の仕事ができりゃ、兄貴たちへの借金もとりあえず返せる。借金を返している間は、ギリギリ生きることを認めてもらえる。それでいいじゃねぇか。また二人でクソみたいな仕事をして、無駄に金を貯めればよ」
ニーノは、嫌な予感がしていた。全身が汗をかき、眼が震えて止まらない。どうか、その提案を呑んでくれと、願っていた。
「嫌です。あのお金は、どうしても嫌なんです。だから、僕の眼を売ってください。迷惑を掛けたお詫びもそれでします。」
「ふざけるな! 俺は真面目な話を――」
「僕も真面目です。眼は要らないんです。もう、僕の人生に眼は要らない。要らないんだから、誰かの役に立てばそれで良いんです」
ニーノは、叫びそうになっていた。
金ならある。いくらでもある。腐ってる金だ。これを使ってくれ。……だが、それに意味は無い。映画は、星と同じだ。フィルムは過去の光を閉じ込める檻でしかない。すでに起こってしまった過去を、いまさら観測しただけの人間に、変える方法など存在はしないのだ。
「あぁ。そうかよ」
チッチは、ロウタの眼を見て、詰まらなそうに呟いた。
/7
季節は春になった。
ロウタは、高そうな、おろしたてのタキシードを着て、街に居た。すっかりやつれたチッチが、その手を引いて歩く。ロウタの表情はとても晴れやかだったが、対照的に、チッチの顔は暗く沈んでいた。
二人が訪ねたのは、ロウタが常連だった音楽屋だった。
「……おう、久しぶりだな」
店主は、その様子を一目見て、大凡のことを察したのだろう。何も言わずに真空管アンプの電源を切り、それから、不機嫌な顔で椅子に坐り直した。
「ずっと、冷やかしですみません。今日は、客として」
「あぁ、そうかい」
店主は、ロウタの眼にすでに光が無いことを悟ったのだろう。いつも視聴していたCD三枚をなれた手つきで集めてきて、そのタイトルを読み上げた。
ロウタが頷いたのをみて、それを袋にしまう。
「――だ。」
店主が値段を告げると、ロウタはポケットから財布を取り出した。馴れた手つきで紙幣を数え、それをカウンターに置いた。
店主は釣り銭と一緒に袋を渡すと、溜息をついて、カウンターの下からもう一つの袋を取り出して、ロウタに渡す。
「これは?」
「お前が言っていた映画の劇伴だ。最近、また流行りだしたみたいでな。稀少だが市場に出回るようになった」
「そうなんですか! 良かった。それで、代金は?」
心の底から嬉しそうに笑うロウタを見て、店主はとても悔しそうに、笑った。
「バカな奴だなぁ――。もう、貰ってるよ」
そう言って、店主は小さな貯金箱をロウタの手に握らせた。それが何なのか、当然ロウタには伝わらなかったが、言葉で伝えるのは無粋だと思ったのだろう。店主は、荒々しく、丁寧に、その貯金箱を引き取ると、小さな声で、サービスだ、と言った。
*****
「なぁ、せっかく金があるんだから、もっと良い席を買ったらどうだ?」
見慣れた長い毛足の赤絨毯の上で、チッチが言った。ロウタは、ゆっくりと首を横に振ると、それを断った。
「自分でチケットを用意するんだって決めてたんです」 取り出したのは、ボロボロの布だった。それだけで、ニーノには全て理解できた。あの瓶のなかに詰まっていた、彼の全財産がこれだ。このために、彼は、ずっと生きてきたのだ、と。
――国立音楽場。内装を見ただけでニーノにはわかる。子供の頃から足繁く通い、音楽家になってからも何度も公演した場所だ。音楽に愛された少年が、その人生を捧げるには最も相応しい場所だ。ニーノはそう思った。
どうか、今日、ここで公演をする誰かが、その願いに応える相手であってほしいと、ニーノは願った。この記録がいつの物だかわからないが、先月であれば、東洋から来た指揮者が、それは見事なベートーヴェンを奏でたと聞く。
せっかくだから、その公演を見てくれたら良い。彼の艱難に報いるだけの、素晴らしい演奏がそこで繰り広げられたら良いと。
「なぁ、ロウタ」
白杖を手に歩くロウタに、チッチが呼びかける。ロウタは足を止めると、わざわざ振り返って、返事をした。
「……おかげでまともな仕事につける。出て行った女房と子供も呼び戻せる。食っていける。だが、本当にこの金、貰っちまっていいのか? せめて山分けに――」
「僕は今日、最高の音楽が聴ければそれで充分なんです。その邪魔になりそうな物は、持ってって貰った方が助かります」
「そうか……。いろいろ、悪かったな」
チッチは、ロウタが振り返って歩いて行くのを見送ると、自分の右の頬を――あの日、ロウタを殴った場所を、思い切り二回、殴り飛ばした。
ロウタは、係員に案内されて、チケット売り場までたどり着いた。贈られたCDの袋と、必死に貯めたチケット代とを、大切に、愛おしそうに抱きしめながら。
「すみません、ニーノ・アバーテの、引退公演のチケットを、ください。多分、これだと立ち見席しか買えないと思うんですが」
――ニーノ・アバーテ。
その、言葉に。ニーノは、全身から汗が噴き出すのを感じた。ニーノ・アバーテ。確かに少年は、自分の名を呼んだ。ありえない話じゃない。つい先日、自分はここで公演をやったからだ。
だが。だが。だが。それは、あまりに、残酷なことだ。
胃液が口までせり上がってくる。いっそこの場で殺してくれとさえ思った。ありえない。あんな、詰まらない三流の公演を、あの偉大な音楽家(マエストロ)に聴かせてしまったというのか。ありえない。ありえない。絶望と嫌悪で、気がおかしくなってしまいそうだった。
どれだけ懇願しても時は戻らない。映画は止まらない。眼を閉じても音が、耳を塞いでも記憶が、ニーノを責め立てる。
まばらな席。しょぼくれた照明。不機嫌な顔の年老いたまがい物の指揮者。あぁ――こんなものは音楽ではない。おざなりに指揮棒が動く。寝ぼけた旋律が周囲を満たす。
「やめてくれ……」
ニーノは、呟いた。やめてくれ。そんな、希望に満ちた顔で、私を見ないでくれ。こんな音楽に拍手をしないでくれ。まがい物の旋律に感涙をしないでくれ。
「赦してくれ! どうか音楽を侮辱した私を赦してくれ」
ついに、ニーノは叫んでいた。
ライフパスを映す端末を投げ捨てて、涙を拭う。
「どうか、もう一度だけ、私に音楽に触れることを赦してほしい……」
それだけを告げると、ニーノは、劇場を飛び出した。
*****
そこにあったのは、万雷の拍手だった。
指揮者の男は、自分の神経が隅々まで研ぎ澄まされていくのを感じていた。久しい感覚だ。拍手の音のひとつひとつが、奏者のすすり泣きのひとつひとつが、聞き取れるようだった。
だれかが、マエストロと叫ぶ。
赦されるだろうか。男は、少しだけ悩んだ。
自分に、この拍手を受け取る資格があるのかと。
「先生、お客さんが呼んでますよ」
背中越しに、声がする。
そうか。彼がそう言うのなら、良いのかもしれない。
男は、無様に流れた涙を荒々しく拭き取ると、客席を向き直った。拍手の音が、勢いを増す。誰かが何かを絶叫する。
あぁ。そうだ。この高揚こそが、この解放こそが。
そして、この寂しさこそが、人生であり、音楽だった。
ようやく思い出せた。
それは、彼のおかげだった。
「ロウタ」
指揮者の男は、先ほど、見事な独唱を歌いきった少年の名を呼んだ。嬉しそうに、少年が頷く。その少年の手を男は無理矢理掴んで、指揮台の上に引っ張り上げた。
「先生!」
「ロウタ。いいや、我が師匠。この拍手はあなたにこそ相応しい。どうか受け取って欲しい」
ニーノ・アバーテは、深く一礼をして、そう言った。
2020年9月21日 映画SF合同 Lifepath with cinema 初出