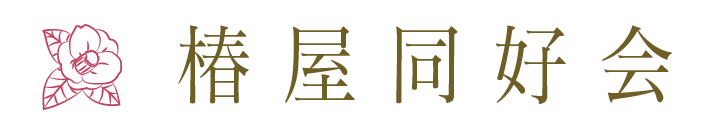アトラースの姫御子、プレイアーデス(昴星)の昇る頃に刈り入れ、その沈む頃に耕運を始めよ。
この星は四十夜、四十日の間姿を隠し、一年の廻るがままに、
やがて鎌を研ぎにかかる頃、ふたたびその姿を現わす。
(仕事と日/ヘーシオドス 松平千秋訳・岩波文庫)
1
スキットルの栓が静かに落ちた。メガロパの白い大地の上に。空いた口から溢れた白い湯気が、落下物のあとを追いかけるようにゆったりと縁を伝っている。熱は拡散したがっていた。より乱雑に。より自由なほうへ。
ぐずぐずしていたら凍りついてしまうのだろう、彼女は水筒の中身をぶちまけると、その場に素早くしゃがみこんで地面の様子を観察した。
「ほら。やっぱり生きてるわ」
スキットル一本の熱湯で、衛星ひとつを茹で上げることができるって信じている少女。地球の知識に妙に詳しく、大人たちが死んでいると疑わないメガロパを生きていると頑なに信じ、そのくせ希死念慮の塊みたいな変な子供。
それが、Yamaという、メガロパでできた僕の最初の友人だった。
「なぜ、生きてるってわかる?」僕はYamaに訊いた。
「だって、赤くならないもの。蟹は茹でられて死ぬと赤くなるものでしょう?」
「それは違うよ」
僕は言う。蟹を茹でると赤くなるのは、熱でほかの色素が分解されるせいで、だから、蟹が死ぬことと色が変わることに直接的な関係はないはずだって。たまたま、僕はその色素に関する知識を持っていたからそう伝えると、「ふぅん」と彼女は興味なさげな返事をして、「でも、その指摘は死んでいる証明にはならないわ」と少し不機嫌な口調で反論するのだった。
2
ピステンJ80が均した片側六車線の工業道路。
宙は吸い込まれるように暗く、起伏の激しい白い大地がどこまでも続く。工業道路の左右に積まれた汚染甲殻屑が詰まったフレコンバッグの土嚢を乗り越えた先の、人工物がほとんど存在しない荒野で、僕らは出逢った。
遥か彼方まで続く白い景色のなかで黄金のごとく輝くひまわりの献花。僕の両親はそこで死んだ。遭難した第6次長期滞在チームの遺体が見つかったその場所には、事故の反省から設置された遭難者向けの0号非常用補給テントの銀幕がメガロパの薄い大気の風に揺れ、いつもひまわりの献花が絶えない。
そんな場所のすぐ隣で、Yamaは子供用の気密服を着て両足を大胆に投げ出し、真っ赤な有線のイヤホンが繋がったSONYのウォークマンを手にして寝転がっていた。
どちらから話かけたのか、いまとなってはもう覚えていない。死体かと思って近づいた彼女のそばには宇宙服を着たシェパード犬がいて、僕の接近に先に気がついたのも、そのライカという犬だった。Yamaは急に傍を離れた犬にまったく驚くことなく、まるで僕がそこに来ることを知っていたかのように、貴族さながら優雅に立ち上がってこちらを振り返った。彼女はスキップしながらお互いのヘルメットが触れあう程に僕との距離を詰めると、
「わたしたちはみんな死ぬ運命なんだよ。死なないことがわたしたちの悲劇」
あどけない声と笑顔で僕にそう告げた。
僕はあまりに突然のことにその言葉の意味するところを理解できなかった。咄嗟に口から出たのは、「変なこと言うね」とか「どうしてそんなことを言うの」とか、そういうどうでもいい言葉だった。そのことごとくを無視して彼女は言う。
「ファイト・クラブ。読んだことある?」
僕は首を横に振った。
メガロパで暮らすただの子供が読んだことがあるわけがない。いまとなっては、それが地球でよく読まれていた小説であることは知っているけれど、産まれた時から木星圏内で暮らしていた僕には、知るよしもない。
彼女はそうやって、地球由来の文化を引用してみせるのが好きだった。たとえば初対面のときにYamaがウォークマンで聴いていたのは、ショスタコーヴィッチの「祖国は聞いている」という、これまたとんでもなくマイナな曲だった。
「ガガーリンが、ヴォストーク1号で地球に帰還するときに口ずさんだ曲だよ」
「地球に帰りたいの?」
「違うわ」Yamaは首を振って毅然と否定する。「いい? 地球に帰るというのは、大人たちの言葉」
「大人たちの?」
「そう。地球で生まれ育った人たちの言葉。生まれた場所が帰る場所というのなら、わたしたちが帰る場所は地球なんかじゃない」
「じゃあ、僕らは宇宙人ってこと?」
「宇宙人?」それが予想外だったのか、Yamaは僕の言葉を繰り返すと吹き出した。「君って、変わってるね」
彼女は立ち上がると、僕に片手を差し伸べて言った。
「わたしと友達になってよ」
3
それから僕は時折管制区から抜け出して、いつもの場所へYamaに逢いに行った。死んだ両親の墓参りに行くとでも言えば僕の境遇を憐れんだ大人たちから簡単に許可が降りた。僕は嘘をついた。でも、悪い気はしなかった。いつも過剰に気を遣って親切な大人たちには、僕は少々うんざりしていたのだ。それに、元々Yamaと出会う以前から、すでにこうやって管制区から逃げ出していたから、その頻度が多少増えても不思議に思う人はいなかったと思う。
その日も、いつもと同じように、僕はその場所にいた。
Yamaはスキットルで熱湯をぶち撒いて、
僕は落ちた栓を拾う。
「きょうは一緒じゃないんだね」
「ライカ?」
「うん」
「集会所で飼ってるんだもの。いつも一緒ってわけじゃないわ」
「そうなんだ」
「好きなの、犬……」
「え? どうだろう」僕は首を傾げた。
あまり、犬に対して好きとか嫌いとか、そういう感情を抱いたことがなかったから、どう答えたものだろうか悩んだ。
「いつもそこにある物が、そこにないから、気になっただけなんだ」
「へぇ」
気にしないで、と僕は言う。けれど、Yamaはどこか満足げに微笑んでいた。
いまの回答のどこが、この変わり者のお気に召したんだろうか。何だか僕は落ち着かなくなって、矢継ぎ早に別のことを訊いた。
「この間話していたけれど、なぜ、この星が生きてるって思う?」
「メガロパのこと?」
「そう」僕は頷く。
「私にはわかるの」
「それじゃ答えにならないよ」
「あなたは、自分のご両親が死んだことを知っている。ライカが生きている犬だってことも知ってる。それと同じだよ」Yamaは両腕を伸ばして伸びをする。「そういうあなたはどうなの? わたしたちが踏みつけているこの大地が、大人たちが掘削して食糧にしているこの星が、生きてるって思う?」
「少なくとも、大人は死んでると思っている」
僕はそう答えた。
ここは高放射線量で汚染されているし、太陽の光だって届かないし、酸素だってない。こんな環境でも生きていけるのはクマムシか人間くらいだ。
「クマムシか人間くらい……」
Yamaは肩を揺らしながらクスクスと笑う。
「だって、そうだろ」
この星は死んでいるから、
火山活動が活発なイオなんかよりもよっぽど安全で、
安全ということは掘削が早く進むわけで、
それに倫理的な問題も考える必要がなくって、
だからこの星は、何かの偶然で蟹の幼生期のメガロパにそっくりな形をしているだけのただの衛星で、決して生き物なんかじゃない。
管制区でそろばんを弾いている大人たちはそんなことを言っていたよ、と僕はそう告げ口した。
「大人ってつまらないわ」
「でも、僕らはそんなつまらない大人たちの子供だ」
「だから大差ないっていうの?」Yamaの瞳がぎらりと光る。「互いに相似な形状をしていて、おおよそ同じ素材から構成された有機体。そうやって社会を構成するうえで必要な共通点をお互いのあいだに見出して安心している。けれどほんとうは、全く異なるもの同士かもしれないのに、みんなそれに目を瞑っているだけ」
「じゃあ、君も僕と違う?」
「えぇ。だって、実際のところ、あなたはわたしと違うもの。そうでしょう?」
Yamaが突然立ち上がって歩き出す。僕は座ってそれを見送った。彼女は徐々に駆け足になっていく。慌てて僕も追いかけようとしたけれど、朝に薄く積もったドライアイスで足が滑ってうまく走れなかった。何度か手をつきながら必死に後を追う。彼女の姿はすでにフレコンバックの向こう工業道路の側へと消えていて、僕は土嚢の山に手をついてよじ登った。
ようやく僕はYamaに追いつく。
遮るものがなくなったことで、ようやく僕の耳にも奇妙な異音が聴こえるようになった。
キャリキャリと金属が擦れるような音。
そのとき、僕はそいつを初めてみた。
質実剛健な大艦巨砲主義、まるで旧い時代の戦艦の
ようなゴテゴテの様相をしたそれは、腕のように生えた円筒状のシールドの先端に刃を備えた巨大な掘削機だった。
工業道路の歪曲した地平線から、そいつの頭だけが覗いていた。低重力帯で降ろされて新しい立坑まで運ばれる途中なのだろう。自動操縦で強化コンクリの道路にキャタピラを擦り付けながら行軍するそれが列を作っている。
まるで、戦車みたいだった。
「すごい。戦車みたいだ」思わず、僕は口に出して言う。
「戦車を知ってるの」とYamaが驚いたようにこちらを振り向いた。
「うん」僕は頷く。「見たことがある。写真でだけど」
それは黒くて大きな鉄の塊。
その重量で人を押し潰し、その火砲で街を砕くのだ。
「戦車はね、投入された初めの頃に目的の秘匿性を確保するために、水を運ぶウォータキャリアなんて名前で呼ばれてたんだ。これは兵器ではありません、人を殺す道具なんかじゃありません、って。でも、ウォータキャリアって略すとW.C.だからWater Tankって呼称にしたんだって」
Yamaは一気にしゃべった。「物知りだね」と驚く僕を無視して先を続ける。
「でも、今じゃタンクは水を貯める道具としての固有名詞よりも、殺戮兵器としてそのイメージが定着している。メガロパで暮らすあなたでも、タンクと聞いて真っ先に兵器をイメージしているのがその証拠。おじいちゃんのおじいちゃんの世代が第一次世界大戦で投入した戦車があまりにも人を殺しすぎて戦争そのものの形を変えてしまった。人間はまた馬に乗って戦争をするべき、なんて意見もあったくらい。でもそうはならなかった」
「なぜ」
「商業として成立してしまったから」
Yamaは僕の質問に歌うように答える。
「『されど、それは血を求め続ける。存在の贈与による負債を返済するために』」
「難しいよ」
「人間だって、同じなんだよ」
「僕らが戦車と同じ?」
「そう。戦車が人を殺すように、私たちは死ぬ運命なんだよ」
ちょうどそのとき、しんがりの車両からオレンジ色の気密服をきた大人が顔を覗かせた。
「乗ってくか?」
僕は首を振る。両親が来るから、といつものように適当な嘘を並べて。
男は肩を竦めると中にひっこんだ。
けれど、Yamaだけは車輌に飛び乗ると手摺に捕まって、
「さようなら」と空いた片方の手を振る。「またね」
「ばいばい」僕もそう言って手を振る。
それが彼女と会話をした最後の機会だった。
その日以降、もう二度と僕がYamaに会うことはなかった。
4
ウェットフードの缶を開けて器に盛る。煙草に火をつけてからライタで灰皿の縁を二回叩いた。その音を合図にライカは食べ始める。僕はその頭を撫でてキッチンを離れた。
突然の来客は、僕の睨みを気にすることなく、まるでここが自宅と言わんばかりにソファでくつろいでいた。
アロハシャツに膝丈のショートパンツ姿。
頭にサングラスを載せていたら地球のハワイあたりでバカンスをしていてもおかしくない格好だ。
日焼けのない真っ白な素足を曝け出し、見せびらかすように長い脚を組んでいるこの妙齢の存在は、衛星掘削行法第26条の要請に基づき管制区から派遣された中央労働区の連絡事務官を務めるヒルダという女性だ。ヒルダは僕の衛星地質学の学位取得に伴う地球留学の際に、死んだ両親に代わって後見人となってくれた女性で、以来ことあるごとに世話になっている。メガロパでのいまの僕の肩書きは中央労働区連絡事務次官、つまりヒルダは僕の直属の上司にあたる。
連絡事務官の職務内容としては、甲殻掘削の施工計画や、放射線反射材として気密服や基地の建材向けに出荷されるメガロパ甲殻屑の品質管理、さらにはその下層から掘り出した新鮮な「身」の部分の衛生管理等があるが、そうしたことは現場が自分たちでやりたがるからある程度放っておくことができる。むしろ、それ以外の生活面、彼らの手が届かない領域の仕事が回ってくるのがこの連絡事務官という職業だ。
つまりは、体の良い雑用係。
たとえばそれには、メガロパの脱皮に伴う避難時において、避難船の数が足りず急遽中央労働区の移動住居モジュール「ヴェスタ」数十機がセパ超深度立坑へと避難先を変更せざるを得なくなった場合に、集団の移動速度をあげるために切り捨てた集会所モジュールで飼育していた貰い手のいない犬をどうするか、といったことも含まれていた。
「それで、いつまで?」僕はゲージのなかで寝ているライカを覗き込みながらヒルダに訊く。
「一週間ほどでかまわないわ。餌とかの消耗品は、念の為二週間分を持ち込んだけど、万が一足りなくなったら言ってちょうだい」
「一週間の根拠は?」
「平時であればここから坑までは数日を要するだけだけど、工業道路が地割れ等で使えない可能性を考慮
した結果」
「了解しました」と僕は言う。「まあ、一週間だけなら」
ヒルダはようやくコーヒーに口をつけた。
「集会所の犬だから、本来なら管理して然るべき人がいるんだけどねぇ」
「だったらなぜ僕に?」
「諸事情で預かれないって」
「諸事情?」僕は腕を組んだ。「というと?」
「死んだ子供によく懐いていたらしい」
「はぁ……、まぁ、わからなくもないですが」
「まぁ、とにかく、そういうわけよ」
「で、同じように諸事情を抱える僕に、何故か白羽の矢が立ったと」
「そう。うってつけでしょう? 君にはたんまりと貸しがあるからね」
忘れたとは言わせないとばかりにヒルダが身を乗り出す。
Yamaは、ある日を皮切りに、僕の両親の墓場から姿を消した。
メガロパでは、行方不明者が多い。甲殻や「身」を掘削中に崩落事故に巻き込まれたケースに加えて、さらに近年増えているのが濃霧による遭難だ。
ヘリウム3を吸って巨大衛星となったカニ幼生の表皮は、本来のカニ幼生の表皮の些細な凹凸から想像がつかないほど峻険な地形となって僕らの前に現れるし、
メガロパの薄い二酸化炭素の大気のために生じる霧のせいで、通信環境が整った近年でも遭難事故が後を絶たない。
行方不明になり捜索が打ち切られた人たちについて必要に応じた追加調査を行うのが僕に与えられた職務だった。言ってしまえば、Yamaを探すための私情だ。そうした便宜が、犬一匹預かるくらいで返済できるものならまあ安いものだと思う。
僕は煙草に火をつけた。
食事を終えたライカが駆け寄ってきた。ヒルダの足元をぐるぐると駆け回ると、やがて僕の隣のソファに飛び乗って丸くなる。
「早食いは消化に悪い」僕はライカを撫でて注意した。
「だったら君は煙草をやめたほうがいい」とヒルダが言った。「犬の健康に悪影響だ」
「わかってます」僕は舌打ちして言う。「これが最後の一服です」
「そもそも、それ、アークロイヤルじゃない。ちゃんと税関通してんでしょうね?」
「クロサワに訊いてくださいよ。僕はあいつから買ってるんで」
「貴重な空気だって汚れる」
「どうせフィルターで浄化されるでしょう?」僕は言う。「それに、よく言うでしょう。真冬に暖房をガンガンに焚いた部屋でアイスを食べるといつもより美味い、って」
「数年間地球に留学したくらいで、文明人ぶるんじゃないわよ」
寝息を立てていたライカが急に耳を立てた。すぐに起きあがると何度も吠え始める。
すぐに、僕の耳にも地鳴りが聴こえた。
「何?」
「衛星震かもしれません」
針山の様相を呈している灰皿に、僕はまだ半分以上残っている煙草を押し付けて火を消す。
直後に、
ドン、という衝撃があった。
しがみついたテーブルごと左右に振られる。
魂を揺さぶられるような揺れ。
マグからコーヒーが溢れ、
照明が音を立てて明滅する。
ライカが幾度も吠えたてる。
ロッカーからガラガラと音を立てて僕らの気密服が倒れた。
建材が軋んで鳴いている。
数分間続いた揺れは、やがて細かな家財同士がぶつかるカラカラという音を僅かに残して少しずつ収まり、今度は痛いほどの静寂が訪れた。
「終わり?」
「違います」僕は首を左右に振る。「脱皮がはじまったんですよ」
「とすると、急いだ方がいいわね。セパ避難坑には私が先に行く。受け入れ施設側の被害状況を確認してくるわ。あなたはこっちに残って、民間人の誘導を」
「了解しました」
5
周囲の被害を確認するために、ヒルダから少し遅れて僕も外に出た。
梯子を登りヴェスタの屋上に出る。管制区に近いこのあたりはここ数年で富裕層向けの居住区として開発が進んでいて、穴を掘ることが本職の労働区とは正反対に、背の高いマンションが乱立していた。しかしいまや入居者のほとんどがカリストに避難しているため、新興のゴーストタウンと化している有様だ。
片側六車線の動脈のあちこちで、ヴェスタや貨物牽引車が煙をあげながら散らばっていた。路肩に頭から突っ込んだり、互いに衝突したのかキャタピラが外れているものもある。事故車両の隙間を縫うように、外に出てきた橙色の気密服姿の労働者が埋めていた。
「動かねえ移動居住モジュールは放棄しろ!」腕章をつけて指示を出している一人に見覚えがあった。
「クロサワ」
「あ? ミハルじゃねぇか」こちらに気がついてクロサワが駆け寄ってくる。
梯子を登ってくる彼に僕は手を貸した。
「被害状況は?」僕が訊ねる。
「見た通りだ。動かないヴェスタはここで放棄だな」
「移動中じゃなくて良かった」
「あぁ。不幸中の幸いってやつだ」
「ヒルダには会った?」
「いや。指示だけ出して、肝心の本人はさっさとどこかに消えた」
「先にセパ避難坑へ行ったみたいだよ。さっきまで僕のところで寛いでたけど」
「あいつ、またサボってたのか」クロサワは鼻の頭に皺を寄せて言う。
「業務の一環さ。犬の預け先を探してたみたいだ。集会所の……」
「あぁ、なるほどな」
クロサワは「ちょっと待ってくれ」と僕に断りを入れると部下に作業に戻るように指示を出す。それから声を潜めて、
「それより、本当か? メガロパは死んでなんかないって話は……。見てみろよ。連中、今回の地震が呪いだの天罰だのってすごいぞ。いままで散々シールド機で穴を開けてきたからな。カニ幼生を象った粘土にナイフを入れて遊んでいたつもりが、全然ままごとじゃなかったってわけだ」
「残念だけど、ただの噂ってわけじゃない」
「単なる地球やイオのような地殻変動じゃないのか? あるいはエウロパみたいに地表が地下の流体の上に浮いていて、そいつの動きによって地表も動いているとか」
「現象としては同じだ。だけど、大地のしたで起きているメカニズムはまるっきり別なんだ。地球のメガロパは稚ガニやその先に成長する過程で何度か脱皮するって話は訊いたことがあるな?」
「J80もそうだと?」
僕は頷く。
メガロパ開発報告書に初めてこの星が冬眠した巨大生物である可能性が指摘されたのは、一年半前のことだ。その報告書では、掘削による質量分布の偏りによって自転軸がずれて、木星からの潮汐力の影響が増大したことが記されていた。
その後、いまから1年前にメガロパ開発報告書によりメガロパの脱皮時期が初めて予想されたあと、かつてYamaがそう信じていたように、いまやメガロパを生物として見る動きが主流となっている。航域労働総会から退避勧告が出てからというもの、カリスト恒久基地から商業地区の建設で出向いていた労働者、メガロパの管制区のスタッフ、さらには食用身の工場の労働者たちが一気に管制区に押し寄せたせいで避難船はずっとパンク状態が続き、僕らのように貧乏で早期出星が間に合わなかった人たちは、管制区の北、メガロパ頭胸部に掘られたセパ超深度立坑、通称「セパ避難坑」に避難することになった。セパ避難坑は初期に掘られた立坑のひとつで、こうした立坑は甲殻の下のカニ身部分まで到達していることから、脱皮時の影響を受けにくい避難場所としてスポットライトが当てられるようになっていた。
「じゃあ、この衛星震はそういうことなんだな?」クロサワが心底うんざりした声で尋ねる。僕は頷いた。
「間違いない。木星の潮汐力によるメガロパの脱皮の前兆だ」
6
クロサワ曰く、再び移動を開始できるまで丸一日はかかるそうだ。僕はライカを連れて少し歩くことにした。Yamaと出会った場所が比較的近かったので、少々足を伸ばして立ち寄ろうと思い立ったのだ。こんな状況でも営業していた花屋に立ち寄って両親の献花台に備えるひまわりの花を準備して1時間ほどかけて向かう。
Yamaが行方不明になった直後の数年は、ほぼ毎日訪れた場所だ。いまは、一応とはいえ社会人になって日頃の業務に追われていることもあり、ここに足を運ぶ回数は減ってしまった。
たった一年訪れなかっただけで、景観ががらりと変わっていた。
記憶のなかの景色の面影すらない。
あろうことか両親の献花場所だった場所は地下鉄の地上駅になっていた。建物ができた直後にこの星の脱皮が判明したらしく、駅の周囲の開発はそこまで進んでいない。
この星の脱皮にによってこの区画も木星の重力に捕らわれたら、ここも木星の大気圏で燃え尽きて木星の燐光となるのだろうか。そのほうが、駅がずっと残るよりは幾分か美しいかもしれない。
駅の入り口には車両が何台も乱雑に放棄されていた。通称「模型」と呼ばれている地球の高級車と同じ見た目のローバー・タクシーが何台も。
僕とライカはその間をすり抜けて駅の構内へと侵入した。
駅宿舎のなかは空っぽで、真っ暗だ。抱き抱えられないほどに太い支柱がいくつも乱立していて、それが天井へと伸びて消えている。僕の立つ地面はホームになっていて、それと平行にいくつもの線路が走っていた。空間の広がりは僕のヘッドライトが届かない場所まで続いている。ライカの息遣いが吸い込まれて消えた。ここでは、僕らはあまりにちっぽけな存在だっだ。
駅構内をぶらついていると、与圧エリア内に黒い影がひとつ。
近づくと、それが女性であること、さらに気密服の頭部を外していることがわかった。何か喋っている。
僕はよく見ようと眉を寄せた。ヘッドライトを点ける。彼女はヘルメットを指さすジェスチャをしてるようだ。僕は腕の端末で周囲の大気密度と気圧を確認した。ヴェスタ内部と変わらない数値だ。慎重にヘルメットを外す。念のため、ライカの気密服は脱がせない。いつでも外に逃がせるように。
けれど、僕の気遣いをよそにライカがぐいぐいと女性のほうへとリードを引っ張っている。
こんな時に、こんな場所にいる人間なんて絶対にまともじゃない。
しかし、けれど、彼女の顔を視認して、後悔がどっと溢れ出す。良く知った顔だった。
確か名前はロアといったはず。Yamaの育ての親だったはず。以前に会ったときよりも随分と痩せて、顔色もいいとは言えない。
「お久しぶりです」と僕は言った。「あの、こんなところで何を?」
ロアは火をつけた煙草を咥えると、僕の質問には答えずに視線だけ横へ移す。そこには第6次長期滞在チームの名前が刻まれた石碑があった。
「人を探してるのよ。彼女、ここによく来ていたっていっていたから」とロアが言う。暗がりでタバコの先端の橙色が数回、明滅を繰り返した。「誰の話か、わかるでしょう?」
「献花台、ここに移っていたんですね」僕はロアから目を逸らして呟いた。「僕が初めてYamaと会ったのも、献花台のすぐ隣でした」
「好きだったのよ。言ってなかった?」
「え?」予想外の返答に僕は驚いた。「何がです?」
「こういう、人が死んだ場所。変わってるでしょう?」疲れた声でロアが言う。
「はぁ……」
「この星では人が死にすぎるわ」
「戦争がないぶん、地球よりマシです」
「死ねば同じよ。労働災害も間接的な人殺しだわ」
ロアは淡々と語った。
「ねぇ、リードを貰ってもいいかしら」
ロアは地面で煙草を揉み消すと、リードを僕の手から受け取って、その場にしゃがみ込んで宇宙服を着たライカを撫ではじめた。
僕は和やかな光景を横目に僕もポケットから煙草を取り出して吸った。
半日ぶりの煙草を僕はじっくりと味わう。住居モジュール内部ではライカがいる限り吸えないだろうから、いまのうちに血液に煙草の旨みを溶け込ませようと試みる。
「名前はなんて言うの?」
「え? 僕?」
そう言うとロアがこちらを睨んだ。それで僕は瞬時に質問の意味を理解する。
「犬はライカです」
「……やっぱり」
「じゃああなたが集会所でライカを飼っていたんですね。なぜ、預かりを拒否されたんですか?」
「秘密。それじゃあだめかしら」ロアは目を閉じて回答を拒絶した。そしてやつれた顔に精一杯の微笑みを浮かべると、
「貴方は、以前会ったときよりずっと生き生きとしてるわ」
その一言で、僕は何も言えなくなってしまった。
Yamaの行方に関する手がかりを探すことで精一杯だったのに、いつの間にか日々の生活が本来の目的を苔のように覆い隠していた。
両親が死んでYamaと出会うまでの僕は、目も当てられないほどに自暴自棄だった。けれどYamaがいなくなってからは、その真逆だ。Yamaを探しているうちに、いつの間にか生きることに精一杯になっている。amaが死んだことを信じきれないせいで。メガロパの極限的な環境で行方不明になってしまったのだから、死んでいるのは間違いようのない事実だ。それはわかっているつもり。けれど、僕にとってYamaは地球でできた友人とあまり変わらない距離感で、僕の中で「生きて」いるのだ。つまり、ただもう一度逢えないというだけ。
でも、目の前のこの淑女の場合は、僕とは違うだろう。養母として捜索の打ち切りの後に死亡に関する手続きをしてきっとイヤと言うほどYamaの死の事実に直面している。 僕は、何とも言えない申し訳なさに襲われていた。
するとロアは「ごめんなさいね」と笑うと、
「別に皮肉のつもりじゃないの。わたしだってね、10年間探してきましたけれど、この星が終わりを迎えるまでの残りたった数日で見つけられるとは思ってないわ」
「じゃあ、なおさらなぜこんなところに?」
「メガロパが脱皮すれば、表皮にしがみついたあらゆる痕跡がロッシュ限界を超えて砕かれてしまう。 もう二度と探せなくなってしまうわけだから、最後くらいせいぜい足掻いてみようかなって思ったの」
7
緩やかな丘の上で急ハンドルを切りタイヤを鳴らしながら対向車線へUターンすると、ロアはそこで車を停めた。1kmほど後方に、無秩序に散らばる僕らの移動基地モジュールが見える。
駅でのやり取りのすぐ後にクロサワから至急戻るように連絡があり、ロアが近くまで送ってくれることになった。駅の前にごろごろと駐車してあった高級車のなかのオースチン・ヒーレー・スプライトの模型、それがロアの車だった。
「悪いけれど、ここからは歩いて戻って」
「送迎をお願いしちゃって、スミマセン」僕はお礼を言う。
「気にしないでいいの。私が言い出したことですから。それとYamaのこと、あまり気に病まないでね」
「あの、あなたはこれからどうするんですか」
「最後に行くところがある。だから合流はできないわ」
僕が車を降りると管制区の方面から閃光があがった。ブイヤ基地の打ち上げ場のほうからだ。
ロアも車を降りてきた。僕らは目を細めて緩やかに上昇する光を見つめた。
「きれいね」
時間を確認する。
あれが最後の避難船の打ち上げだろう。
旧い時代の自己着火性推進剤が火を噴く。
入植時代から受け継がれてきたエンジンだ。
エネルギー効率が悪ければそれだけ美しく見える、熱と光の非効率な芸術。
たった数分で燃え尽きるハイパーゴリックの太陽だ。
僕らの影がメガロパの白い表皮に長く投影された。
しかし、それもすぐに消えてしまうだろう。
「始めは泣き叫んで、最後は静かに消えていくもの」
ロアが静かに呟いた。
「なぞなぞ?」
「なんのことかわかる?」
発射場から遅れて届いた振動と轟音がすっかり消え去ると、ロアはそんな質問を僕に投げかけた。僕は静かに首を振って、答えを待つ。
「私たちのことよ。人間の話」
「はぁ……」
「なぜだと思う?」
「何が?」
「どうしていなくなるときは静かなんだろう、って」
「泣くのと死ぬのを同時にこなせる人はいませんよ」
「死んだら、何もかも終わりかしら」
「養分くらいにはなるんじゃないかな。ここに草木はないですけど」
「夢がないのね。若いのに」
「夢なんて、死んだ人間が見るものです」
「さっきと矛盾してるわ」
「そう……、しかし、こんな矛盾は、きっと、序の口です」
「そうね、その通りだわ、ほんとうに……」
「これを」僕は気密服の外ポケットから貨物用追跡
タグを取り出して、彼女の手に握らせた。メガロパの軌道上に存在する衛星測位システム「ガリレオ3」と地表のメッシュネットワークを利用した位置情報サービス。タグの内部情報は僕がアクセスできるから、万が一何かあってもある程度ならロアの居場所がわかる。非常時ですからと言って僕は彼女に半ば押し付けるように渡す。すると、「じゃあ、交換ね」と言ってロアは撫でていたライカを抱き上げて僕に寄越した。
「……避難坑で合流したときに、その端末と交換する条件でライカを引き渡します。ちゃんと来てください。約束ですよ」
「わかった。じゃあね、ライカ」ロアはハンドルを握る。「君も。元気で」
「別れの挨拶はしない主義なんです」
「変なひとね。バイバイ」
オースチン・ヒーレー・スプライトの真っ赤なテールランプがメガロパの薄い霧のなかに消えていく。僕は抱き上げていたライカを地面におろした。
「さあ、僕らもいこう、ライカ」
8
その後は相変わらず竈の神の名前をもつ移動住居モジュール「ヴェスタ」での移動が3日ほど続いて、予定より早くセパ避難坑へ到着した。例のゴースト・タウンでの停車中に管制区から街の物資の受け渡し許可があったそうで、水・空気・食料・医療パッチ、さらには燃料となるヘリウム3を大量に確保できたとヒルダが喜んでいた。クロサワも、人気メニューがゆえに消耗のペースが早いステーキや海鮮類のメニューを補充できたと満足げだった。
先日の衛星震で少なくない数のヴェスタ損害を受けた影響で、いくつかのヴェスタでは乗り合いを余儀なくされていた。僕の住居モジュールも例外ではなく、クロサワが住み着いている。昨日も今日も彼は我が物顔で寛いでいるけれど、冷蔵庫に彼の住居モジュールから持ち出した酒と食糧を持ち込んだ功績があるわけで、僕としてもとくに文句があるわけではない。
クロサワはテーブルの脇を横歩きですり抜けて冷蔵庫を開けると、片手で瓶ビールを二本取り出し、そのうちの一本を僕に放り投げる。それからまたテーブルに着席すると再び缶詰を開けてビールをあおりだした。しかし、美味しいものを食べているのに、難しい顔をしているのは、どういうことだろう。僕がその理由を訊くと、
「セパ避難坑に、どうも俺たちのヴェスタが乗り入れられないそうなんだ」
と再び特大のため息をつく。セパ避難坑の街一つ分の直径を持つ巨大な縦穴と、その周囲に立ち並ぶガントリークレーンが視界に入る距離まで来たというのに、僕らはまたしても長い列を作って移動を停止を余儀なくされていた。どうやら、その原因は、受け入れ先のトラブルだったようだ。
「昇降機がダメになっちまったらしい。この間の揺れのせいで故障したって話だ」
面倒くさいことになったな、と僕は思った。恐らくこの後、僕らは移動住居モジュールをすべて放棄して、最小限度の手荷物だけ抱えて徒歩か小型車で避難坑内部へと移動することになるだろう。セパ超深度立坑の外縁部から内部にかけて造られた螺旋状の通路を辿って。それには時間もかかるし、何より搬入物資制限がキツい。
「どのみち数十時間はこのまま待機ってわけだ。まぁ飲めよ。お前も」とクロサワが言って、栓抜きを僕に投げてよこす。「どうせ、持って行けやしないんだ。両手に収まらない分は胃に詰め込まなきゃ損だろ。ひょっとしたら避難が間に合わなくて、これが最後の晩餐になるかもしれないしな」
「……クロサワ」僕はキッチンにビール瓶を置いて名前を呼ぶ。「僕らのあとにきた奴らはどうなるかな」
「どうだろうな。これから来る奴らは、正直ここの避難穴に並んでも間に合わないかもしれない」
聞いていた話と違う。予定じゃ僕らの入坑は明日だったはずだ。
そう訴えてもクロサワは肩を竦めて、
「決まったものは仕方がないだろう。状況が変わったんだ」
「ガリレオ3の携帯端末を貸してくれ」
「はぁ? 何に使うんだ?」
「早くしろ!」
「お前も持ってるんだろ。自分の使えよ、全く」ぶつくさ言いながらもクロサワが端末を投げてよこす。
「ありがとう」
僕は自分の端末で在留認証IDを確認して、クロサワの端末にも同じ内容を入力する。
ふたつの端末に、まったく同じ情報が表示された。
僕らが停車しているメガロパのセパ超深度立坑付近にひとつ、それからゴーストタウンにひとつ。
嫌な予感があたって背中から冷たい汗が一気に噴き出る。ここ数時間、どちらのドットもそこから移動した気配がない。
「クロサワ、車を貸して」
「はあ!?」
「ちょっと出掛ける用事ができた」
「どこに」
「街まで行く」
「街って中央のか?」
「そう」
「馬鹿野郎!」
「怒鳴ったってどうしようもないだろ」
僕はそう言い返しながら気密服を着ていく。あまり時間に余裕はない。メガロパの近木点までもう30時間程度しかないのだ。
「なぁ、諦めろって」クロサワが僕の前に立ち塞がる。「何を忘れてきたのか知らないが、そもそもお前、あんまりものに執着するタイプじゃないだろ」
「ものじゃない。人なんだ」
「……人だって? まだ逃げてないやつがいるのか? 街に?」
「そうだって」
「冗談だろ?」
「冗談だったらよかったんだけど」僕は言う。「大真面目だ」
9
ヒルダには僕から連絡を入れた。未収容の人員がいるため確保に向かう旨を伝えると、彼女はクロサワとライカも連れていくように僕に命令した。
クロサワが運転を申し出てくれたけれど、血中アルコール濃度が高くて車両のロックが解除されない。結局、ライカとクロサワを後部座席に乗せて僕が運転することにした。
道中、僕はロアに関する情報をクロサワに共有した。
「その追跡タグで、せめて生きてるか死んでるかくらいわからないのか?」
一通りの説明を終えると、クロサワがそう訊ねてきた。
ただの貨物追跡用のタグにそんなことができるわけがない。
住人のいないゴーストタウンではメッシュネットワークの精度もあまり期待できないだろう。位置情報サービスも、脱皮に伴う地形変化が著しいせいで地図があまりあてにならない。そう説明するとクロサワは、厄介だな、と言って黙り込んでしまった。
ガラ空きの工業道路ではヴェスタでの行軍の数倍の速度を出せるおかげで、街までは1日もかからなかった。休憩を挟まずぶっ通しで来てしまったので、到着後、僕は真っ先にライカを車から降ろして、自由にしてあげた。片側六車線ある工業道路のど真ん中にAKIRAさながらに停車した僕らの車を尻目に、宇宙服を纏ったライカがどこまでも駆けていく。
「どこから探す?」クロサワが言う。
「この間はあそこで会った」僕は地下鉄の地上駅を指
さす。工業道路を挟んで反対側にゴーストタウンが
広がっている。
「駅か……」
「うん。戻ってくると思うか?」
「情より科学に頼れよ」
「それが役に立たないって説明しただろ」
「くそっ! 本当に手間だな」クロサワが舌を打つ。「どうやって探す」
「手分けしよう。俺が駅を探す」
「了解」僕は頷く。「僕は団地を」
クロサワが駅に消えていくのを確認して、僕は車の
ドアを2回叩いてライカを呼び寄せる。
ゴーストタウンはいまだ街灯がついていた。この街にはまだ電気が来ているのだ。おそらく街を巡回する蟹型監視カメラ「カニカム」のインフラ維持か、あるいは上層部にまだメガロパの脱皮を信じきれていない人がいるのかもしれない。
僕は足元を通り過ぎるカニカムをむんずと一匹捕まえてひっくり返すと、腹に隠されたインジェクタからヒルダから教えてもらった管理者IDでカニカム経由で警備局のデータベースに侵入する。僕のヘルメットのフェイスカムに保存してあるロアの顔写真を顔判定データに加工して、カニカムが蓄積したここ三日間の共有録画データベースに検索をかけた。最後に捉えられたロアの移動経路をカニカムにインストールして、僕はカニカムをそっと石畳のうえに戻す。横歩きで移動を始めたカニカムを僕は追いかけた。カニカムは、団地のなかの立派なマンションのエントランスに入るとエレベータに乗り込もうとした。衛星震が怖いので、僕は一度カニカムを拾い上げて、エアロック仕様の非常用階段を登っていくことにした。
4階でカニカムに反応があった。僕は重い扉を開けて中に入る。フロアの赤い絨毯が敷き詰められた廊下の壁には、数カ所に緊急時には部屋から出ないよう促す注意書きがあった。それからエントランスと階段の間の気密扉が機能しない場合、廊下の空間が一時的に低圧状態にさらされる可能性があるらしい。注意書きに目を取られていたせいで、肝心のカニカムを毛の長い赤いカーペットの海で見失ってしまった。しかし、代わりにライカがロアの気密服の匂いを嗅ぎつけた。
扉をじっと見たまま動かない。
409号室。
僕はインターホンを鳴らす。
もう一度。
反応はない。
ライカが吠える。
僕は扉にIDを翳して、長方形のハッチ式のドアのハンドルをゆっくり回す。扉が滑って開いた。
センサを確認した限り、室内の気圧・大気組成に問題はなさそうだ。さながら人間のために創られたビオトープだ。僕はライカのヘルメットを外してやった。
ライカはキャンキャンと鳴きながら廊下を弾丸のように駆けていく。反応を見る限り、たぶん、当たりだ。
ロアは、ここにいる。
僕はヘッドライトを点けたままヘルメットを脱ぐ。
「すみません!」
真っ暗闇にジンジンと自分の声が響く。
返事はない。
玄関正面のリビングがヘッドライトで不気味なコントラストに染まった。
室内は広く、あちこちに本が積まれていた。
リビングのほかに幾つかの部屋があるみたいだが、奥の部屋からは香水とは違う甘ったるい匂いがしていた。
壁掛けの姿見に僕の全身が映った。反射した光が眩しくて僕は俯く。
足元でルンバが僕に何度もぶつかっている。
細菌を見つけた抗体のように。
僕を排除しようとしているのだろうか。
すぐにクロサワを呼んで合流するべきか迷った。けれど、リビングのテーブルの上を見たときに、そんな思考は吹っ飛んでしまった。
傷だらけの、赤いウォークマン。
Yamaが持っていたのと同じ。
僕はルンバを跳び越えてテーブルへ駆け寄る。バッテリは生きていて電源が入った。
僕はウォークマンをまるで洗礼を受ける赤子を扱うように両手で持ち上げた。SONYのロゴが画面のなかで踊った。震える指で楽曲リストを操作する。
ショスタコーヴィチのドルマトフスキーによる四つの歌、作品86。イヤフォンから『祖国は聞いている』が流れ出す。
初めて逢ったときにYamaが口ずさんでいた曲。
ガガーリンが初めての宇宙から地球に帰るときに口ずさんだ曲だよ、とYamaが話していた曲。
あぁ、ほんとに、なんてことだ。膝から力が抜けて、僕はその場に崩れ落ちた。瞼を閉じると、僕の内に存在していて、しかし忘れていた記憶が匂いを持ってまざまざと蘇える。
溢れた涙をルンバが攫っていって、僕は自分が泣いていることに気がついた。
四曲全てが終わるまで僕はずっとそうして蹲っていた。
楽曲リストの一番上に、ボイスメモ01“Mother”というのを見つけた。録音されたのは6時間ほど前。
僕はおもむろにそれを再生する。
ロアの声が、流れ出した。
10
汝の弟の血の声地より我に叫べり。
血が流れると、人間はそこに何かしらの合理性を見出そうと試みる傾向があることは、あなたにならわかってもらえるかしら?
みんな、誰かの死や流れた血が、単なる消耗や犠牲ではなく、社会の役に立つ何かであると思いたいのです。たぶんそれが宗教や物語や文明を創り出す原動力になっているのでしょうね。この星で誰かを失った人は、おそらく永遠にこの星に捉われ続けるでしょう。つまり、こうも言えます。親しい者の血が流れた場所、それが故郷なのだと。それは神性を科学技術が覆い隠した世界で、数少ない本当の信仰となり得るでしょう。娘の遺体は見つかっていないけれど、やはり私にとって娘はもう死者なのです。この点が、私とあなたのYamaに関する認識の差でしょうね。
脱皮によってこの星からYamaの生きた証が消えてしまうのなら、私もここで終わりにすることに決めました。リビングの本とウォークマンは全て差し上げます。どちらも元はYamaの所有物で、ほとんど使ってません。この音声は最後のわがままです。聞き終わったら削除してもらって構いません。
ミハル。願わくば貴方が、これを見つけて聴いてくれますように。
11
そして僕はようやく気が付く。
部屋に充満した甘い匂い。
ライカが吠えている。
ロアの寝室で。
倒れたグラスと注射器。
ベッドからだらりと垂れた素肌の腕。
タンパク質の腐りかけた甘い匂い。
クロサワに連絡を試みる。
しかし、何度かけても出ない。
「クソッ!」
僕はリビングに戻って、ソファの上に躰を投げ出す。
ドッと疲れが湧き上がってくる。
目を閉じてしまおう。次に瞼を開けたときには、
すべてが綺麗になっているはずだ。
何もかも……。
12
遠くで犬が吠えている。
そのおかげで一気に目が覚めた。
飛び上がって、腕の端末を見る。数時間が経ってしまっている。
僕は慌ててライカを呼びつけて、吠え続けるライカを撫でて落ち着かせてやった。
すぐにここを出なくてはいけないだろう。
ロアの死体は連れていけない。でも、今後の処理に最低限必要な情報はヘルメットのカメラが記憶しているはずだ。僕はリビングのウォークマンをポケットに突っ込んで、ライカを連れて部屋をあとにした。
エアロックを出ると、通信が回復し、大量の着信があった。クロサワとヒルダからだ。僕はヒルダに折り返し通信を試みた。
「よかった。繋がった。そこから動かないで」
「すみません」僕は端末越しにヒルダに謝る。「状況は?」
「こちらの収容は完了してる。もう甲殻後縁部が割れたらしい。脱皮が始まるわ」
「もう、そちらに戻ってる時間はないですね」
「ロアという女性は? 見つかったの?」
「ええ。死んでましたが。おそらく自殺です。部屋の状況のデータは送りました。遺書の音声データも」
「了解した。とにかく、喫緊の問題はあなたたちよ。とくにミハル。あなた、大丈夫? 何かあったんじゃない?」
「大丈夫です」
「クロサワがそっちに向かってるから、階段を降りて2階で合流して。207号室に入室後、あなたたちはそこで脱皮完了まで待機。その団地の基礎はかなり深い。だから倒壊の危険は低いと判断した。外にいるよりも安全よ。脱皮後の甲殻はおそらく1時間でロッシュ限界を超える。それまでに軌道上で待機している救助チームを送るわ」
「ありがとうございます」
「生きて帰ってくること。いいわね」
「了解しました」
通話越しに僕は頷いて、来た道を戻る。
片手にライカのリードを。
片手には書物を。
寝起きで躰が重い。
階下から足音がして、手擦りから覗き込む。
気密服に身を包んだ男が片手をあげてあいさつする。クロサワだった。僕もやあ、と声をかけようとして、
突然バランスを崩した。
それは、かつてないほどの大きな揺れのせい。
僕の躰は宙に浮き、
本は崩れ、
カニカムを咥えているライカと目が合う。
慌てた様子のクロサワが階段を駆け上がる。
僕を受け止めるつもりか?
しかし、間に合わないだろう。
間に合わないことばかりだ。
目を瞑る。
内臓が浮く感触。
宙ぶらりんだ。
どちらでもない。
メガロパでも、地球でも。
クロサワがいた場所に、Yamaの幻影が見えた。
Yamaが僕を抱きしめようと手を伸ばしている。
僕はYamaに手を振った。
さようなら。バイバイ。
しかし、
僕の帰る場所は、どこにある?
13
慣れない新鮮な空気で目が醒めた。
冷たい空調の風を遮るように薄いブランケットを肩まで引き上げる。
ここはどこだろう。
起きあがろうとすると、首が痛んだ。
「大人しくしとけ」
男の声。クロサワだ。
ライカが僕の頬を舐める。
「どうなった? どこだ、ここは?」
「救助艇のなかだ。お前、もっと食った方がいい。担ぐのは楽でよかったが、不健康な軽さだ」
「どうして、ここへ?」
「お前……」クロサワが呆れたように目を細める。「ヒルダの話、聞いていたか?」
「そうだ、ウォークマンは?」
「拾えるもんは拾った。そこに置いてあるから、後で確認したらいい。っておい!」
僕は躰に鞭を打って無理矢理起き上がった。
赤いウォークマン。それからオマケでカニカムまである。僕はほっと息を吐いた。ゆっくりとベッドがわりの長椅子に戻る。
「彼女、たぶん最初から死ぬつもりだったんだ。だからライカをヒルダに預けたんだと思う」
「俺たちはできることをやった。そもそも、本来は俺たちの仕事じゃないだろ?」
だから気にするな、とクロサワは言う。
「僕も一応、管制区側の人間だ」
「違う。落ち込むべきなのはもっと上の連中だって話だ」クロサワが僕の肩に手をおいた。「あの状況下じゃあ、俺たちの手には余るだろ。俺たちに責任はない」
それよりも、あの女だ、とクロサワが言う。
「娘とは会えたのか?」
「どうだろう」僕は答えあぐねて、ゆっくりと言葉を探す。幸い、時間のリミットはここにはない。「Yamaは、たぶん死に囚われた人間の前に現れるんだ。マニ教のダエーナーみたいに……。だから、彼女が両親を失って自暴自棄になった僕の前に現れたように、多分ロアが死ぬ直前に会えたんじゃないかな。Yamaは根本的に僕らとは違う存在で……、でも、人格的存在として解釈すると、やっぱり僕らと同じ人間なんだ。両親がいて、空気を吸って、水を飲んで、食べ物を食べなければ生きていけない」
「枯れ尾花の正体は幽霊だったと?」
「うん。だけど、その逆もちゃんと正しいんだ」
クロサワは僕の頭を数度軽く叩くと、立ち上がって丸い窓枠から外を眺め始めた。僕も立ち上がってその横から外を見る。視界いっぱいに木星が広がる。
「でかいな……。なんかデカすぎてよ、今ならお前の神秘主義的な与太話も信じられそうな気分になるぜ」
「この船はどこへ?」
「カリスト恒久基地に向かうそうだ」
「戻ってこれるかな」
「ビジネスになる限りはな」
ロッシュ限界を超えた脱皮殻が、無数の流れ星になって木星へ吸い込まれていく。
「綺麗だ」と僕はつぶやく。
クロサワは僕が目醒めたことを報告するために去っていった。足元ではライカが丸くなって眠りについている。
窓の外でスラスターが噴射されて、救助艇が僅かに振動した。この船がメガロパの軌道から離脱し始めるのだ。脱皮を終えたばかりの透き通った新生メガロパが遠のいていく。
みるみる小さくなっていくメガロパの透明な蒼い双眸を僕はいつまでも見送り続けた。