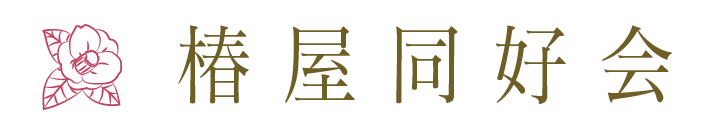SPY SEEDS #1
SPY SEEDS #1
瀞昧幹
/1
――250。
260、270……とても良いペースだ。あと5秒もあるし、新記録も夢じゃない!
蝋谷あられちゃんと目が合う。頷いた彼女が、さらに速度を上げていく!
「……すごい、すごいよあられちゃん! 反復横跳びで300回を超えるなんて!」
「そそそんんんななな、てててれれれちちちゃゃゃうううななな」
「凄い……動きが早すぎて声が三重に聞こえる……これなら世界記録も狙えるよ!」
「シュ――……違うよまひるくん。こういうのは、ギネス記録っていうんだよ」
右手で握ったラチェットカウンターが350の数字を示し、煙を上げていた。
「やった! 新記録だあられちゃん!」
「くふふ、いぇい」
反復横跳びの構えのまま、最高の笑顔でダブルピースをするあられちゃん。
やばい……めちゃくちゃ可愛い。
「まひるくんにしか私の動きを正確に計測できないから、いつもありがと。でも、みんなには内緒だよ?」
「大丈夫さ。きっと早すぎて、逆にゆっくり見えてるはずだから。扇風機みたいにね!」
体育館内で発生したソニックブームにクラスのみんなも少し動揺していたけど、誰もあられちゃんが起こしたものだとは気付かない。
そう、これは二人だけの秘密なのさ。
「くふふ、ありがと。はぁーあ、動いた動いた。集中するとつい本気出しちゃうんだよね。記録には適当に70回くらいで書いてほしいな」
「それでもかなり多いけど、分かったよ。俺に任せて」
体力テストの記録ボードを壇上まで提出に行くと、首をかしげる先生と目が合った。
「な、なぁ鯖江くん。いまの凄い音は……?」
「さぁ……天井に挟まってるボールが破裂したとか」
「ああ、なるほど! 先生はてっきり、木更津駐屯地からスクランブルが飛んだのかと思ったよ~」
「はは、またまた。基地が近くにあるってだけで、わざわざ路地谷高校の上は飛びませんよ」
「なっははは、それもそうか」
「ははは。大袈裟なんすから」
俺は先生との問答をかわして、体育館の壁際で休んでいるあられちゃんのところへ戻った。
はぁ、あられちゃん……運動が大好きで、夢中になるとついソニックブームを起こすカニ股の君。こんな素直で可愛い子と、普通の学園生活を送りたいぜ!
そのために……俺はこの夏、一皮剥けてみせる。
「おつかれさま、あられちゃん。……あ、喉乾かない? 汗拭きシート使う?」
「んっしょと……ん、なぁに?」
開脚前屈しているところからキョトン顔を上げるあられちゃん。脚をほぐすのに集中していたようだ。
目標に向かって全力直進、普段からストイックに打ち込むところも、超魅力的だぜ!
「どしたの、まひるくん」
柔軟体操をやめて、壁に背を預けて座るあられちゃん。
「あーうん。べつになんでも、あはは……って、あられちゃん! あし、あし!」
「え?」
俺はすぐに、自分の目を覆った!
「ま、また……開いちゃってるから」
「ん? ……あ、わぁっ!」
あられちゃんが脚を閉じたのを見計らって、俺はさりげなく隣に座った。
「……見た?」
「な、なにが……体操服だし、なにも見えてないよ」
「まひるくんのえっち……」
「えっ! ち、ちがう、そんなつもりは」
「くっふふ、冗談。気を抜くと脚が開いちゃうの、なかなか直らなくて。教えてくれてありがと」
これちょうだい、と言いながら、俺の汗拭きシートを一枚捲り取った。なんだかドキドキする。
「あ~きもちぃ。男子ってスース―するやつ好きだよね」
スラッと伸びるきれいな脚が、あられちゃんの手で拭われていく。俺は思わず目を逸らしてしまった。
くそぅ、なにをしてる俺、一皮剥けるんだろ。
もっと会話しないと……そしてあられちゃんを、アクアラインデートに誘うんだ!
「ね、ねぇ、あられちゃん。今週の土曜日……」
「はぁーぁ、陸上部でも思いっきり走れたらなぁ」
俺の声が小さすぎて届かなかった……挫けるな俺、話の流れで誘えばいい。
「えっと、上手くいってないの? 陸上部」
「うん、ちょっとね。夏の大会にも出られなかったし」
「え!? あの脚力で選抜されないの!?」
「そ。わたし、前を走るのが苦手なの」
ほら、とⅤの字に投げ出された両足が……――ぐっ!
……あられちゃんの脚を見ていると、なんだか右手が疼いてくるぜ。
おい、おい。鎮まるんだ、俺の右手!
「勝手に動くな。こら、大人しく――」
「……まひるくん? 私の話、聞いてる?」
「え!? あ、ああごめん! なに?」
右手を床に叩きつけて、あられちゃんに向き直る。
「もう~。女子の愚痴だからって、頷いてればいいと思ってるんでしょー」
「そんな! ちゃんと聞いてるから」
「ジト~」
「ほんとだって、ね? 前を走るのが苦手なんだよね。理由は、分かるの?」
「んん? ……あー。分かんないけど、顧問は成長期のせいじゃないかなって」
成長期。なるほど。
「そのせいで……まっすぐ走らないといけない陸上部だと、いつも補欠なんだよね」
「そ、そうなんだ……それは、勿体ないな」
こんなに……こんなに良い脚を、持ってるのに。
「……あられちゃんも、生まれつきの体質で悩んでるんだね」
「ええ~? ふふ、なんでまひるくんの方が深刻そうな顔してるの。まひるくんは、まっすぐ走れるでしょ」
「あ、あっはは。そうだね……うん」
……どうだろう。
俺は、まっすぐ進めているんだろうか。
この“右手のせい”で、俺の学園生活は……。
「まひるくん? どうかし……ひゃ!」
「え? なにあられちゃ――おわぁあ!?」
思慮から覚めると、俺の右手が……あ、あられちゃんの太ももを勝手にタッチしていた!?
「やっ、な! なにしてるのまひるくん!」
「ああちがう! ごめん違うんだ、右手が勝手に」
「かかか、勝手にぃ~!?」
「あ、ちがう! 右手は関係なくて。そう、無意識で」
「無意識に……ふとももを……っ!」
「わわわ! そういう意味でもなくてドハァ!!?」
あられちゃんの横蹴りが炸裂、俺は床に伸びてしまった。
「もう、やっぱりまひるくんのえっち! 真面目に話してたのに、もう知らない。ふんっ」
そう言って、あられちゃんは横歩きで体育館を出ていった。
「まってぇ。ちがうんだ……右手が、勝手にぃ……」
うう、くそぉ……。
デートに誘うどころか、あられちゃんに嫌われちまったよぉ!
――この、この右手さえなければ~……!
「ぐぬぬぬぅ……ん?」
握り拳を睨んでいると、手の甲の皮膚がボコボコっと波打った。
「そろそろ限界か……はぁ」
俺は右手を脇に隠して、終業のチャイムとともに体育館を離れた。
/2
昼休み。誰もいない廊下の隅で、俺はシャツの第一ボタンを開けた。
この――……“右手のカニビル”に、自分の血を吸わせるために。
「ほら、もう出てきていいぞ」
俺が合図すると、骨を鳴らしながら右手がぐにゃりとたたまれて、指の水掻きが繋がった。
手首より上が一本の触手になり、頭から吸盤みたいな形をした口が生えてくる。
「んっぱぁ~~! カプッ。じゅ、じゅぅ、じゅぅ~~~……っキシャーーー! 生き返るワー」
少しフラッとする俺をよそに、しおれ気味だったカニビルの野郎はムクムクと張りを取り戻した。
「ヒェイェイェ~イ、まひるよぉ。ビルちゃんのシニョリーナはどこ行っちまったのん!?」
「うるせぇ。お前が勝手に動いたせいで、またあられちゃんに嫌われちまった。もう散々だぜ」
「そうプンスコんなってぇー兄弟。こちとらモーニング抜かれて喉が渇きっぱなんだヨ」
大袈裟に口をすぼめて干し肉みたいになってくる。
「お前の夜更かしスマホのせいで寝坊したんだぞ。視界がチカチカして眠れやしねぇ」
「イェア。あのツイート見たかまひる? ショットガンで片栗粉液を撃っても貫通しないGIFのヤーツ」
「眠くてあんま覚えてない」
「マ? VTuberのマンぼっちーが生配信で紹介してたろ。あれダイラタント流体っていうらしいゼ、ビルちゃん癖になって40回は再生しちゃった」
うるせぇ……。
「趣味が合わん。あと勝手に投げ銭してないだろうな」
「安心しナ。昨日は350円で我慢シタ」
「おう、上出来だ」
「350円を10回シタ」
「おう。……おう? おう」
考えるのが面倒くさくなった。
吸血を早いとこ済ませるために首を晒すと、カニビルがいつもの歯形に食いつく。
「ふぅ……スマホ、あんまり使い方が酷いとパスワード変えるからな」
「あぐ! あぐあぐアグルル~」
はぁ、なんだか子供をあやしてる気分だ。
「ほら早く吸えよ、貴重な休み時間なのに」
「おけマル。じゅ~~~」
吸血を続けるカニビルを横目に、俺はポケットから“お弁当の劇薬ドリンク”を取り出した。
それを味わうことなく喉に流し込んで……はい、俺の昼飯は終わり。
空容器をしまって、入れ替わりにスマホを握った。あられちゃんへのゴメンネメッセージを考えるためだ。
「じゅ~……ウメ、ウメウメ、ウ……飽きた」
だぁー、またゴネゴネがはじまった。
「生まれてからまひるの血しか飲んだことなくてヨぉ、そろそろ大人の味を知りたい年頃だよナ~?」
カニビルが視界に割って入って、あられちゃんのLINEアイコンを物欲しそうに眺める。
「ダメだ。何度も言わせるな」
「なんでだヨ、あられちゃんが最推しだからかぁ?」
「……お、推しとかは関係ない。他人の血はダメだ」
「そう言わずサ。オレもまひるもカノジョを吸いたい。心は同じ、ならもうタッグしか勝たん」
「組まない。それに、変な言い方するな。あの子のことは、こう……吸いたいとか、あんまりそういうノリで話したくない」
「うぃ~、言うねウブ騎士くん。でもそうやって守ろうとしてるのはカノジョ? それともプライド?」
「デリケートなところなんだっ。ふん、カニビルには分からんさ」
「安心しろ。スポーツ女子との会話はインスタで予習済み。アドバイスは任せナ」
「え、まじ? ――っておい! お前また勝手にアカウント作りやがったのか」
「昨日はJKとお婆ちゃんからDMきたぜ。写真もめっちゃ褒められるし、ビルちゃん愛される才能あるみたい」
「会う約束とか絶対するなよ……」
「てか、ビルちゃん分かったわ。まひるヨぉ、あられちゃんはお前にとっての清楚枠ってヤツだな?」
「う、う、うるせぇ~~~!」
両耳を塞ごうにも、右手がカニビルだから大声を出すことでしか対処できない。
「はいはい、クソ分かりますデスワ~。だから体育館で全肯定ムーブかましてたんだ」
「そんなっ、ふざけ……」
「ヒュ~、赤くなったナ」
「だれが!?」
「たしかに、わかるぜ? カノジョの締まった筋肉、ぷりっぷりのカニ身みてぇな脚、腰つき。逆立ちしてでも食いつきてぇヨナ。ああ、堪んねぇぜ!」
こいつ、脚まわりしか見ちゃいねぇ……。
「お前と一緒にするな。あられちゃんにはもっと良いところがあるんだ」
「へん、手に入らなきゃ意味ナイだろ」
つーん、と頭がそっぽを向いた。この野郎……。
「にゃ~ぁ、ビルちゃん情けねぇゼ。この宿主は雑食のくせに貪欲さってものがない! そんなだから今までガールフレンドも」
「言うな! ……それを言うな、虚しくなってくる」
口をむず痒そうにくちゃくちゃして、へにょ~んとだらけるカニビル。
「……そうダナ、オレらは運命共同体。オメーにこのまま春が来なけりゃ、この愛らしい土筆ヘッドも一緒にしおれてくんだぜ。ガルルル」
「なにが土筆ヘッドだ、どっちかというと」
「は? なに。は?」
「……悪い。ちょっと言い過ぎるところだった」
ちょっと、な。
「ハン、いいさ。ビルちゃんは純潔の血を啜るユニコーン・カニビルになるんダ。略してカニコーン」
「ドヤるな」
「知ってるか? あと十三年このままでいれば、オレたちゃ魔法使いになるんだぜ」
忙しい形態変化だな。クソが。
「カプ、じゅ~~~」
「……ったく、このところ吸血の量も増えやがって。他人の血の味を知ったカニビルがどうなるか、分かったもんじゃねーぜ」
「じゅぅ……は~ぁ。欲張りは言わねぇ、一度でいいからカニの血を吸いて~ナ」
「なんだそれ。好みがあるのか?」
「カニビルだからな」
「あっそ。やっぱ趣味は合わねぇーな」
くそ。いつもこんな調子で振り回されっぱなしだぜ。
ここ最近は特に、抑えていても勝手に動くし、右手が疼く頻度も増えてきた。いつまでも俺のスネ齧り、いや、首筋齧りでいられるのはごめんだぜ。
うーん、どうするべきか……あっ。
「……そういえばカニビル。お前にも成長期ってあるのか?」
「ハァン? なにが言いたい」
「なんかこう、分かるだろ。体の変化を感じるとか、そろそろ独り立ちしてぇ~みたいな」
「なにソレ、思春期のドギマギ的なハナシ?」
「真面目な方のハナシだ」
「にゃ~……分かんネ。オレには親がいないからな、自分が将来どんな姿になるかもワカンない。カニビルってことくらいしか知らネ」
分かりやすくフイッと頭を逸らして、その話はしたくないって仕草をしてくる。
「いや、いるだろ。俺とカニビル、共通の……あの親父が」
「――やめナ。まひるの親父は、もう死んだんだ」
……少し、胸の辺りがズキっとする。
確かに、あいつは……俺をこんな風に生まれさせた、クソ親父だけどさ。
「んっん。そんな言い方ないだろ。それに、親父とはまだ話せる」
「はぁ? ……まひる~、また“アレ”やるつもりか?」
「仕方ないだろ。親父以上に俺たちの生態を知っているやつは、いなんだから」
時計を見る……そろそろ昼休みが終わる時間だ。あられちゃんには、ちゃんと会って謝るか。
あられちゃんのLINE画面から戻って、俺は別のメッセージ画面に飛んだ。
「放課後……屋上で、いつもの頼む……っと。よし」
スマホをポケットに入れ、第一ボタンを締めた。
/3
――放課後。
屋上の扉を開けると、夏の夕焼けが目を焦がした。鼻先で、東京湾の潮風がここまで届くのを感じる。
右手で斜陽を遮りながら進むと、逆光に浮かぶ一人のシルエットがあった。
腕を組んで仁王立ちをする幼馴染……三住蘭だ。
「……まひるヨぉ。ビルちゃん何度でも言うけどサ、どうかと思うぜ? 死んだ奴と話すなんて。怪しすぎるしよぉ」
「怪しくない。蘭は本物の霊媒師だ。もう何回も降ろしてもらったから、分かるだろ」
「そういう問題じゃネェ。できたとして、死んだ人間と話すのもどうかと」
「静かにしろ、もう手の形に戻れ。蘭にもカニビルのことは話してないんだから」
「ふーん……」
しゅるるっと静かに形を変えた。俺はそのまま、右手を振りながら近づく。
そこには、早くもイタコの装束に身を包む蘭がいた。
「――よぉ、蘭。待たせたな」
「……ほんとよ、まったく」
早速本題に……と思ったら、不機嫌そうにツンツンとした蘭の返事。あれ、なんで怒ってるんだ。
「何分待たせたと思ってるの?」
「え? えっと、集合は18時だった……よな?」
カニビルを説得するのに時間がかかった。確かに約束ギリギリだけど、そんなに怒らなくても……。
「ちがうわ、まひる。私があんたのためにどれくらい待ったかって聞いてるの。放課後すぐ、重い荷物をここまで運んで、道具も並べないといけないし、着替えもしなきゃいけないわ、この風の強い青空の下ね」
「お、おう……」
「コホン。とにかく、150分に渡ってずっと準備をしていたの、ここで、ひとり、わたしはっ」
「あーごめん! 分かった、悪かったよ」
「……それだけ?」
「えっと……俺はどうすれば良かったんだ」
「考えてみて。私のためにどうすれば良かったか」
右手がプルプル震える。くそ、カニビルの野郎、笑ってるな。
「うん。俺も早く来て手伝うべきだったかなぁ、と思うけど。でもそうすると、蘭の着替えに鉢合わせる可能性があるぞ」
「っ――……そう、そうね」
「ああ、そうだろ」
「……」
……? なぜか、蘭の顔が赤くなる。
「つまり、どう思うのよ」
「え……まさか、俺に着替えを……?」
「はっ――んぁああ! もう、ばか!」
「いてっ。……え?」
なんかワサワサと鳴る棒で叩かれた。大丈夫かそれ、儀式で使うやつだろ。
「そこはこう、『ばか、誰か来たらどうすんだ。今度から俺が見張るから、準備も手伝わせろよな』くらい言いなさいよ」
「ええええ」
なんだよそれ、俺にはちと難易度が高いぞ。
【――ちなみにまひる】
勝手に喋るな……。
【イタコちゃんの模範解答には及ばねェが、過ぎたことは問われちゃいねぇ。あの子は自分の心配を一番にして欲しかっただけだと思うぜ】
え……。あ~~、そういうことだったのか。さすがインスタフォロワー2万人は伊達じゃない。
「なにか言った?」
「いえ! あはは。心を込めたオウム返しは、誠意に欠けると思うので……だから、その、うん。都合よく呼び出して悪かった」
「それでよし」
蘭はワサワサ棒を肩に背負うと、いろんな雑貨を並べた円陣のなかに入った。
「黄昏時だわ。……はじめるわよ」
蘭は宣言すると、印を何種類か結んで、ぼそぼそと呪文を唱えながらワサワサ棒を振った。
「んん、この手応え……まひる、あんたのお父さんを降ろすのは、今日は5分が限界よ。聞きたいことは準備してきた?」
「ああ。もちろん」
蘭はそれを聞くと、返事をせずにその場に座った。
そして掠れの多い呼吸を始め、スゥ――、フゥー――……と、口笛の一歩手前みたいな心地良い音色が、俺の鼓膜を震わせた。
「んっ……ん」
コクン、と首の座りが落ちる。すると、間もなくゆっくりと姿勢が上がった。
振り返った蘭の眉間は……険しそうに皺が浮いて。
その眼光は、間違いなく俺の親父――鯖江不一、その人だった。
「やぁ、まひる」
数か月ぶりにしては簡単なご挨拶だ。
早速聞きたいことを問い詰めたいが。その前に!
「父さん! ……いや、クソ親父。なんであんたは、俺をこんな体にしたんだ」
「また、その話か」
息子の体を勝手に改造しておいて、まったく悪びれねぇなこいつ。
「父さん、あんたは変わってしまった。生命誕生の起源を追う第一人者だったあんたが、変な研究にまでのめり込んだ結果がこれだよ!」
「まひる。仕方なかったのだ。人類の新たな可能性を発見してしまった私は、それを試さざるを得なかった」
「“ざるを得なかった”ことはないだろ! なんで、俺をこんな身体に」
「人類の進歩のためだ」
話が通じねぇのか? ……いや、いまだに信じがたいが。悲しいかな、“元々こういうヤツ”なんだ。
「ふざけんな。見ろよこの右手を! これじゃ進歩じゃなくて、ち……いや……そうじゃなくて」
「まひる。無理をしてはいかん。使い慣れない下ネタはちっとも笑えないように、その体を拒絶することはお前を不幸にする」
父親らしいアドバイスをもらったところ悪いが、そんな煙に巻くような電波論文はもううんざりだ。
「この体を受け入れたって不幸だ。あんたのせいで、1日3回、このなんだかよくわからない薬を飲まなきゃいけないはめに……」
「まひる、お前の健康のためだ」
この海水にクソを混ぜたような味の薬が!? ふざけやがって!
「気安く呼ぶんじゃねぇ! お前なんかもう、親父でもなんでもない! ……くそ、くそっ、この右手、取れないのかよ!」
「悪いが、子供の頃から何度も言っているように、取り除くことはできん」
「一生このままだっていうのか!?」
「本当に申し訳ない。そうだ」
なんだか、怒りが一周して虚しさが沸いてくる。
「まひる。それよりも、重大な話があるのだ」
それより!? いまこいつ、それよりって言ったのか!
「もういいかげんにしてくれ! 物心ついてない頃はなんとかやってきたけど、このところカニビルの本能が強くなって、おかげで俺の青春は台無しだ! こんなの耐えられない、切断してでも取ってやるからな!」
「聞いてくれ、まひる。時間がないのだ。声が届くタイミングで伝えねばと思っていたことがある。誰かに襲われたりしていないか。その学校に無警戒でいるのは危険だ、お前は狙われている」
「は、はぁ? いったいだれが」
「私が施したカニビル適合手術によって、お前には<第六感>が与えられている。お前の”血”が疼くということは、周囲に吸血対象が――つまり、シーフード怪人が潜んでいる可能性が非常に高いのだ」
「ん、え? なに」
「カニビルの好物、シーフード怪人だ」
「は? ……なんだよそれ、どういうことだよ! 潜んでるって、なんで!」
「さぁな」
「それもお前の仕業か!? なにしてくれてんだよ!」
「……」
「なんとか言えよ」
「私にも分からん」
……。
「なぁ父さん……頼むから、たまには真面目に話を」
そう、俺から口火を切ろうとした――その時!
「キャア―――――――――――!!!」
っ……!!!
遠くから、誰かの悲鳴……!
「ゆけ、まひる。シーフード怪人を倒せるのはお前の吸血しかない!」
「はっ……父さん、いきなりなにを言って」
「いいからやれ!」
「あぁ……んもう!!!」
俺はなにも考えず、その場を駆け出した!
/4
「はぁ、はっ……この辺りのはずなんだけど」
悲鳴が聞こえた方角を頼りに、右手がより疼くままに走ると、屋外プールの建物前にたどり着いた。
プールサイドに繋がる石階段を駆け上がる!
「おいまひる」
「うぉわ!」
ニョキッと俺の視界に割って入って、危うくこけるところだった。
「ちょ、勝手にカニビルになるなよ!」
「近ぇぞ……ガルル、感じるぜ。これまで以上にナ」
「な、は? なにが」
「オレの、好物の気配だ」
「っ――おっちゃらけてる場合か! 悲鳴を聞いたろ、誰か襲われてるかもしれないんだぞ!」
シーフード怪人だか知らねぇが、親父の研究関連で誰かが傷つくなんて耐えられない。
「俺しかどうにもできないなら、早く行かないと!」
「落ち着け。そこを曲がると、もう“いる”ぜ」
――ドチャッ……と、プールの方で鈍い音がした。
どちゃ、どちゃ。滴る水。
不規則なリズムで、何かがにじり歩く音。
咄嗟に身を隠した……そしてゆっくり、片目で覗き込むと――
「ハァァア……フゥンンンォォアアア――」
……低い呻き、ヴヴヴと腹の中にまで響く重低音。
全長3mはあろう体躯の巨影。しっかりと生える筋肉隆々な四肢と、分厚い尾ひれの前傾姿勢。
そして、大きな四角い頭部。
「……ありゃ、なんだ」
「まひる。こいつは鯨だぜ」
こそこそ声で、カニビルが俺の頭に乗ってきた。
「くじら? ……でも、歩いてるぞ」
「ああ。シーフード怪人、鯨ウーマンだ……!」
どちゃ――動きが止まって、何かを探るように頭を振っている。
俺はゆっくり、そう、ゆっくりしゃがんで、柱に隠れた……うん。
「はぁ――――……やばい」
「オイ、なにしてんだまひる」
「想像してたんとちゃう」
「ああ、めちゃくちゃウマそうだナ。じゅる」
「ちゃんとバケモノのフォルムじゃねぇか。てっきり、俺とカニビルみたいな感じだと……」
「ビルちゃん閃いた。カノジョお茶に誘おうぜ? オレはおでこの広い子はタイプなんだ。ツイッターやってないカナ」
「待て、いろいろ待ってくれ……まず、あれ女の子なのか?」
「おう。スク水を着てたしナ」
「まじ?」
もう一度、二人で柱の影から覗く。
ちょうど鯨ウーマンが、プールに飛び込んでいるところだった。
柱の影に戻る。
「着てたわ」
「な?」
「めっちゃ綺麗なフォームだった……」
「鯨だからナ。マジ映えるワ、スマホ貸して」
「ああ~~もう……そうだ、悲鳴の子は?」
ヤツが泳いでいるのをいいことに、半身を出して周囲を一望した。
んん、それらしい人はいない。ちゃんと逃げ切れてればいいが……。
そうこうしてると、プールの水面が盛り上がって、プシャーっと潮が上がった。
「ウィ~。カノジョ誘ってるゼ」
右側からカシャシャシャシャと連写のシャッター音が聞こえる。
「どうしよ……どうしよ……」
「ほらほら、声をかけるんダヨぉ~」
ぐい、ぐいっと右手が体を引いてくる。
「まて、まてよ! あんまり、仲良くなれる気がしないんだけども」
「ウヘ、ウヘヘ。かわいいおでこちゃん、ウマソ……」
「カニビル? ……どぁ!」
引っ張られる力が増して、右手の疼きが強くなる!
「ちょっと、おまえ、なに勝手に!」
「ガルル、ガルルル」
俺のスマホが、床に落ちた。
触手の境目が肘まで浸食して、頭は、吸盤みたく円形に生え揃った歯が剥き出しに変化していく。
こいつ、まさか!
「やめろ! 俺の声が聞こえないのか!」
「ガルルルル」
とうとう柱から引きずり出されて、足取りはまっすぐプールの鯨ウーマンに向かっていた。
俺たちの存在に気付いたのか、黒い影がこっちに旋回しているのが見える。
「ダメ! だめだめだめ」
「ワカッテルヨ、血ハ吸イマセン、ワカッテルヨ」
なんだ……カニビルの様子がおかしい。
まずいぞ。親父が言っていた通りなら、好物のシーフードに反応してるんだ!
「――ブォォウンンンォォオオ……」
鯨ウーマンまでも威嚇に呼応したのか、水面から頭を出し、尾ビレを蹴って勢いをつけてきた。
とんでもなく素早い突進。追随して高くなる波。
あのデカブツ、こっちに乗りあがってくる気か!
「ばかばかばか! 離れろカニビル……え?」
「ガァルルル!!!」
触手の口がミチミチと裂けて、鋭い歯がトラバサミのように開いた!
ジャグリッ――ぶつかり合うインパクトの音にはそぐわない、刃がくいこむ鈍い音。
突進と同時に乗り出してきた鯨ウーマンの頭を、膨張したカニビルが受け止めていた……!
「あぐ、あぐ……さすがに皮が堅ぇナ」
閉じ切れない口を力むと、歯の刺さっているところから鯨の体液が垂れてくる。
「ゴァァ……フォォァアアッ……!」
両腕を伸ばして抵抗する鯨ウーマン。すると、腕立て伏せの構えで上体を起こし、体重に任せて圧し掛かってきた!
抱えきれなかった俺の姿勢が崩れる――そのまま全身が鯨の顎に覆われ、プールサイドと挟まれた!
「うあ! つ、潰れる、潰れる!」
「あぐぐ、グァグググ……」
息が苦しいっ……これは、かなりまずいっ。
「か、カニビル! なんとかしてくれ!」
「ヌゥ……血ィ、血ィィ……ガルルルァアウ!」
――咆哮。とともに、ぶちぶちと筋肉が千切れる音。
右手を見ると……大きく開かれたカニビルの口から、筒状の骨が二本っ、飛び出てきた!?
なんだ、あの形――まるで散弾銃みたいな。
――直後。銃声にトマトをぶつけたような鈍い破裂音が、肩の付け根まで迸った。
「えっ――――」
ゼロ距離でカニビル弾を食らった鯨ウーマンが、声を上げる間もなく怯む。そして力が抜けたように、そのままプールへ滑り落ちた。
あぶくが波立つ水面の上に、血の混ざった液体が浮かんでくる。
「おい……おいカニビル! やりすぎだぞ!」
「グェ、グググ、グェ、グェエ」
右手を見ると、数本に増えた触手がギチチと歯軋りを立てながら絡まっていた。
「なんだよこれ……」
こんなの、初めて見る形だ。なにがなんだか!
いや、いまはそれよりも――
「あいつ、大丈夫か……」
ポコポコと水面のあぶくが増えて……沈んでいる?
「まひる、ケハ、ケハ! ……早ク、引っぱり出セ」
「カニビル!」
触手のうち一本が口だけになって話しかけてきた。
「カノジョは鯨だ、エラ呼吸じゃなイ……!」
「わっ……くそ!」
その意味を理解する前に、俺はプールに飛び込んだ!
――水中は、比重の違う液体がドロドロと浮かんでいた。恐らく、鯨ウーマンのだ。
視界をかき分けていくと、黒いものが見えた。俺の力で引き寄せられる体重か分からないが、やるしかない。
カニビルへ目配せして、プールサイドに触手を巻き付ける。そして左手が、鯨ウーマンの皮膚に当たった。
くそ、つるつる滑る。掴める場所はないか。
とにかく手を動かしまくっていると、指になにかが引っ掛かった!
右手を二回引いて合図すると、カニビルの触手が縮んでいく。
「――んぷは! はっ、はぁ……!」
息つく間もなくプールサイドに乗り上がりながら、全身と一緒に鯨ウーマンを持ち上げる。
「早く、早くぅう――――え……?」
すると、左手の手応えがすり抜けるように軽くなった。
指に掴んでいたものを揚げる……スク水?
呆然としていると、プールの波が対岸の方に盛り上がっていくのが見えた。
そして鯨ウーマンが、逆側のプールサイドに飛び上がる。
「ホゥゥゥ……フゥゥゥ……」
25m先でもはっきり見える巨体が膝をついて、横目でこっちを睨んでくる。
頭からは、カニビルにつけられた傷からテカテカする黄金色の体液が漏れ出ていた。そうか、あれは鯨油か!
右手だけがカニビルの俺より、相手はかなり完全な海産生物に近い状態みたいだ。
あんなの勝てるのか、俺だけで。
「んくっ……」
固唾を飲んで睨み返す……。
――すると。鯨ウーマンは尾ビレで地面を叩き、背面飛びのフォームで屋外プールの柵を超えていった。
え……逃げた、のか?
「はぁ、はぁ――……はぁ~~~」
思い出したように疲れが押し寄せて、俺は仰向けに倒れた。
拝んだ空は、嫌味なくらいに綺麗な夕焼けが覆っている。
「死ぬかと思ったぁ……」
未だに思考が整理できずに狼狽していると、元の触手に戻ったカニビルがニョキッと視界に入ってきた。
「……ギリギリだったナ」
「ああ……そうか? 楽勝だったろ」
「ハ、ハハ? そう……ソウダナ」
「なんだよもう、調子狂うな」
歯切れの悪そうなカニビル。普段がうるさいから、落ち込んでいると凄く分かりやすい。
「……スマネェ。さっきのオレは、本能にとり憑かれたみてぇに」
「いい。もういい……血は吸わなかっただろ」
「でもヨ! 兄弟の言葉が聞こえネェくらい、カノジョに夢中になっテ。……自分でもチョット引いたゼ」
「ははは。でもあの、右手で掴みながらのショットガンは男のロマンって感じで、まじクールだったぜ」
体が落ち着いたのを見計らって、俺も姿勢を上げた。
「ありがとヨ……あーでもちょい待って。もすこしゆっくりした方がいいカモ」
「なんでだよ、ここに居ちゃまずい……だ……ろ?」
――制服を絞りながら駆け出そうとすると、視界がぐわんっと回って、地面が真横になった。
あれ……俺、倒れたのか。痛みの感覚がなくて、自分でもわからない。
景色に色がなくなって、内側から寒気もしてくる。
「まひ――……まひる! ――チッ、貧血が――」
カニビルの声まで途切れ途切れで……重力がなくなったような、ふわふわとした解放感。
俺はそのまま、眠りについた。
つづく。